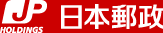社長室通信
Vol.39
1月21日(金曜日)、増田社長とグループ本社社員との意見交換会を開催しました。
日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命でDX関連施策を担当している社員3名が参加し、「DX推進における現状とあるべき姿」というテーマで意見を交わしました。
社員からの主な意見
- DXに正解はなく、立てた計画が2、3年後に意味をなさなくなってしまうような早い環境変化の中で、計画よりも如何に適応していくかが大切。できあがったゴールに向かっていくのではなく、変化しながら進んでいくマインドが必要。
- RPA・AI等の活用により業務を見直し、定型的な事務作業を自動化することで、DX推進に注力できる環境を整えることも大切。商品・サービス面は当然として、社員の働きやすさに繋がるDX推進にも経営資源を配分すべき。
- DX推進にあたっては、リスクを避ける組織風土の改善も必要。人事評価制度を抜本的に見直して「やらないと損」という形にすることで、社員のやりがい、働きやすさ、生産性の向上にも繋がる。
- 挑戦のためには心理的安全性の担保が重要。失敗は「通れない道を明らかにしたというある種の成功」と捉え、複数回挑戦できるよう経営陣にバックアップをしてもらいたい。
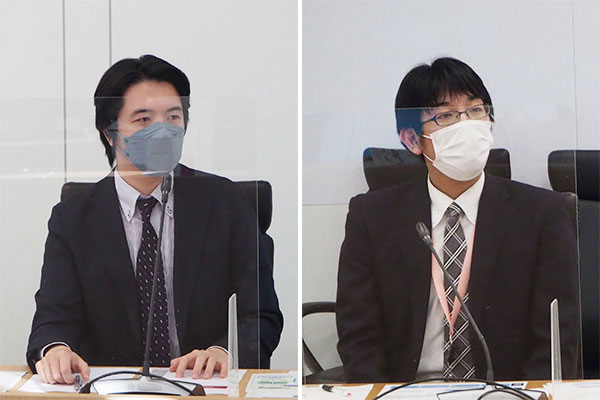
増田社長からのコメント
- 色々な機能をデジタルに置き換えるだけでなく、仕事の手順がガラッと変わり、我々の仕事における住む世界が変わるということを前提にDXを推進していかなければいけない。
- 失敗を恐れる組織風土を変えていくことも重要な観点。総論として「失敗しても良いのでチャレンジすべき」と言うことは多いが、組織・制度面でも色々なことが上手くいくよう仕組みを考えていきたい。

社員からの主な意見
- 社会環境の変化、お客さまや社員の声に柔軟に対応できるよう、アジャイル的な働き方を進めている。DXの戦略を考える上では、社内各部門の壁を飛び越え、お客さま目線でカスタマージャーニーを検討することが重要。
- IT部門、業務部門、経営陣、外部の協力会社などが一堂に会して、闊達に議論できる環境が大切。一つのテーマについてみんなで深く議論できる場があれば、話が進みやすく、挑戦したいというマインドも生まれてくる。
- 新たなサービスをまずは一部のお客さまにご案内して反応を見るなど、お客さまの声も聞きながら、サービスを育てていくサイクルが作れればよい。このような文化を作るためにも、経営陣も含めたDXの研修や浸透策に取り組んでいくことが大切。

増田社長からのコメント
- システム面などは、必ずしも内製化に拘るのではなく、外部の力を取り入れて伸ばしていくことが必要。自前主義に拘りすぎないようにしていかなければいけない。
- DX分野の研修については、内容やレベル感は様々あるが、専門部署や新規採用者だけでなく、経営陣も含め、標準化していく必要がある。

参加者の感想

- 立場の壁を強く意識することなく、伝えたかったことをしっかりお伝えできました。また、増田社長がDXの意識浸透に強い関心を持っていることがよく分かりました。

- 限られた時間ではありましたが、増田社長とお話しする貴重な機会でしたので、業務への意欲が向上しました。

- 増田社長が聞きながらメモを取っていただいたり、社長の考えを踏まえて関心事を質問いただいたりして、お話しできて良かったと感じました。
意見交換会を振り返って
(増田社長)

- グループ各社でDX関連業務を行っているみなさんから、普段の業務の中で考えていることや、グループが目指すべき方向性のアイデアなど、幅広い話を聞くことができました。DXは一つの手段であって、そのことによって何を成し遂げるのか、そういった構想力が非常に重要です。いただいた意見はしっかりと今後に活かしていきたいと思います。
今後も日本郵政グループ社員と増田社長との意見交換会を定期的に行ってまいります。
開催模様については、随時発信していきますので、ご注目ください。