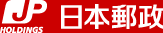全国の郵便局ネットワークを通じ、皆さまの生活の基盤を支える社会インフラとしての役割を着実に果たし、地域から愛され、お客さまから選ばれる日本郵政グループを目指します。
地域社会
全国の郵便局ネットワークを通じ、皆さまの生活の基盤を支える社会インフラとしての役割を着実に果たし、地域から愛され、お客さまから選ばれる日本郵政グループを目指します。
人的資本
日本郵政グループにおける人的資本経営の実践に向け、中期経営計画「JP ビジョン2025+」に基づく経営戦略と人事戦略を実現するための基本的な方向性を示すものとして「グループ人事方針」を策定しました。本方針を通じて、お客さま、地域及び社会への貢献の拡大と、企業価値の向上につなげていきます。
人権
国連「ビジネスと人権に関する指導原則」などの考え方に基づき、「日本郵政グループ人権方針」を策定し、同方針のもと、人権尊重の姿勢を示すとともに、人権啓発活動を推進していきます。
お客さま
郵政ネットワークの安心、信頼を礎として、民間企業としての創造性、効率性を最大限発揮しつつ、お客さま本位のサービスを提供し、地域のお客さまの生活を支援し、お客さまと社員の幸せを目指します。
サプライチェーン
サプライヤーに求める具体的な取組内容を示す「日本郵政グループCSR調達ガイドライン」を策定し、サプライチェーン全体で人権、労働基準、環境などの社会的責任にも配慮した調達活動を推進。