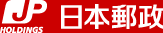- 現在位置:
- 日本郵政ホーム

-
日本郵政株式会社の社長等会見

- 2025年6月27日 金曜日 日本郵政株式会社 社長会見の内容
2025年6月27日 金曜日 日本郵政株式会社 社長会見の内容
- [会見者]
- 日本郵政株式会社 取締役兼代表執行役社長 根岸一行
- 【社長】
- 一昨日、6月25日をもちまして、日本郵政取締役兼代表執行役社長、グループCEOに就任をいたしました根岸一行でございます。メディアの皆さまはじめ、関係者の皆さまのご支援を賜りながら職責を全うしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。また、これまで同様、定期的にこのような会見を行ってまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
まず冒頭、日本郵便における点呼業務未実施の事案につきましては、お客さまの信頼を損ない、また、ご不安とご心配をおかけしておりますこと、グループを代表して、改めておわび申し上げます。
一昨日、6月25日に日本郵便におきまして、国土交通省から一般貨物自動車運送事業の許可の取り消しおよび軽貨物についての再発防止の徹底を求める安全確保命令の処分を受けたところです。また、総務省からも、日本郵便株式会社法に基づく監督上の命令などを受領したところです。今回の行政処分を厳粛に受け止めまして、点呼の適正実施、あるいは飲酒運転の根絶に向けて、グループを挙げて取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
先般、6月17日の日本郵便の千田前社長の会見でもお伝えいたしましたとおり、日本郵便におきまして、トラックでの集荷、運送などの業務につきまして、約6割をほかの運送会社へ委託し、残りの4割は日本郵便が所有する約3万2,000台の軽四車両を使用することとしているところです。トラック全てを使用しないというオペレーションを行う必要がありますけれども、現時点ではオペレーション上の問題は特に発生しておりません。引き続き、お客さまにご迷惑おかけしないように取り組んでまいります。
また、現在、軽貨物車、いわゆる軽四輪車の特別監査が国土交通省により実施されているところです。その処分内容が明らかになった際には、対応するサービスの確保策とともに、改めてご説明をさせていただきたいと存じます。
本日、私が就任後初めての会見でありますので、足元、日本郵政の社長として取り組むべき課題を幾つか述べさせていただきたいと思いますが、現状、何よりもグループガバナンスの徹底が必要な状況です。
これまで、前体制の下でも、一定程度ガバナンス強化が進んでいる面はあろうかと思いますが、今般の点呼問題、あるいはクロスセルの問題、保険の認可前勧誘の問題と、法令などに違反する事案が続発しているところです。したがって、この問題が最も優先して取り組むべき課題として捉えております。まずはグループ全体の体質改善、これに全力を注ぐことが責務だと思っております。
その上で、現在、中期経営計画「JP ビジョン2025+」につきましては、最終年度ですので、これをしっかりとやり切った上で、新たな進路、指針として実現可能な将来に向けた成長戦略、つまりは次期中期経営計画の策定をしていきたいと思っております。
次期中期経営計画は、通例ですと、来年の5月ごろに公表させていただく予定ですが、その概要、骨子につきましては、できれば年内にお示しをしていきたいと考えております。その中では、物流事業や不動産事業といった成長分野にしっかりと取り組み、今後もそれについては必要な投資を行っていく、こういったことが肝要であると思っており、その点も含めての内容になるのではないかと考えております。
ただ、いずれにしましても、まずはこうした成長戦略の検討もグループのガバナンスがあってのものです。その徹底に最優先で取り組み、その上で、人口減少などを控えておりますので、そうした社会問題に各地域で私どもがお役に立てるように、グループとして取り組んでいきたいと考えているところです。
私から冒頭、以上でございます。
- 【記者】
- よろしくお願いいたします。冒頭、社長のご発言でもありましたけれども、点呼の問題、クロスセルの問題などですね、グループ内で不祥事が相次いでいます。特に点呼問題では、おっしゃっていたように、国土交通省の処分、軽トラックについても今後処分が想定されているというところで、郵便物流サービスへの影響も懸念されています。これだけの不祥事を招いている、この一連の事態の受け止めというもの、あと、ガバナンスの強化ということをおっしゃいましたけど、具体的にどう進められていく決意なのか、改めてお聞かせください。
- 【社長】
- まず、点呼の未実施については、点呼の記録簿について虚偽記載もございますので、極めて重大な法令違反だと認識しております。日本郵便は社会的なインフラを担っている運送事業者ですので、その日本郵便の存立に関わる重大な事案だと受け止めているところです。
したがいまして、まずは点呼の確実な実施ということが必要ですが、ガバナンスという意味では、一つのものが解決策になるわけではなくて、例えば研修一つ取っても、単にその研修をやればいいということではなく、研修の内容がちゃんと理解されているかどうか。研修を受けた管理者が郵便局に持ち帰って、それを自分の言葉で社員に伝える、そういったアウトプットも含めての実態、実質のある研修を行う必要があります。それから、システム対応についても、まだまだ遅れているところがありましたので対応をすること。モニタリングの強化も、単にモニタリングを強化すると言っていても、全く効果がありません。今回もはんこだけ押していればそれでよしとしたような、そうしたモニタリングは、中身が機能していなかったわけですから、実態がどうなっているかを確認できるような意味合いにおいてのモニタリングの強化が必要です。ほかにもいろいろなものがあろうかと思いますけれども、そうした具体的な中身を一つ一つ精査をしまして、ガバナンスの強化に取り組んでいきたいと思っております。
いずれにしましても、今回のような事案を改めて考えますと、一つのことで何か事足りるということではなく、複合的に至らなかったところがあった結果だと思っていますので、そうした問題を一つ一つ解決していくこと。一義的には日本郵便の問題になろうかと思いますが、重要な事案ですので、持ち株会社である日本郵政としましても、しっかりとその状況について把握をし、そこに足らないところがあれば是正をすべく、持ち株会社としての機能をしっかり果たしていく必要があると思っております。
その上で、お客さまにご迷惑をおかけしないということ、他の運送会社様への委託や自局の保有の軽四輪車を活用して、オペレーション上ご迷惑をおかけしないこと、これも重要ですので、万全を期していきたいと思っております。
今の時点では特段問題はなかったとしても、これからお中元期などを迎えますと、やはり物量の増加もありますし、それから委託先様の事情として、期間としては短い期間しかできないと、こういったことも出てこようかと思いますので、そうした事案一つ一つに対応することで、お客さまにご迷惑をかけないということが重要だろうと思っております。
それから、国土交通省より安全確保命令が出ておりますが、これは直ちに車両などの停止処分が下るものではなくて、軽四輪車について、しっかりと再発防止策を徹底せよということです。いずれにしましても、まだ国土交通省からの軽貨物に対する特別監査が行われている中ですので、その処分がどういった形で出るかは存じ上げませんけれども、どのような処分が出たとしても、これを厳粛に受け止めて、従来同様、お客さまにご迷惑をおかけしないように万全を期していきたいと考えているところです。
- 【記者】
- 二つお願いします。一つは、点呼問題についてですね、複合的な要因があるということですけれども、第三者による、いわゆる第三者委員会による調査についてはどのようにお考えでしょうか。原因をよく究明して説明すべきではないでしょうか。これが一つ目です。
- 【社長】
- 何か具体的な施策について、第三者からコメントやご意見をいただくことは、今後あり得るかもしれませんが、今回、正直申し上げまして、できていなかった点については、研修の不十分さ、徹底の不十分さ、チェックの仕方の問題、あるいはモニタリングの問題など、問題点がかなり明らかになっているかと思いますので、第三者委員会を設けて検証するような形というのは、必ずしもそぐわないのではないかと思っています。
ただ、いずれにしましても、いろいろな形で、例えば、取締役会でも社外の方がいらっしゃいますし、こういった方々も含めてご意見をいただきながら、適切に対応していくことで、足るのではないかと思っています。
- 【記者】
- ありがとうございます。今の点ですけれども、点呼の問題にかかわらず、先ほどおっしゃったグループガバナンスの在り方で、要するに、不祥事が多発している背景には、やっぱり郵政独特の組織風土というのがあると思いますので、そういう面で第三者に検証してもらう必要性はないでしょうか。
- 【社長】
- おっしゃるように、例えばはんこが押してさえあれば事足りるとするようなところ、あるいは研修に対しての不十分な部分、これに対しては、点呼の問題だけではなく、共通する問題だろうと認識しております。したがって、今回改めてそうした部分を全面的に見直すつもりです。原因を究明して、第三者委員会で検証して、全部駄目ですよと指摘されるまでもなく、全体として取り組んでいきたいと思います。
それから、日本郵便の問題がメインであろうかと思いますが、例えば社員の声の取り扱いの仕方、あるいは内部通報ですとか外部通報、こういったところについても、不十分だった点については十分認識しております。これも点呼問題に限らず明らかになった点です。ただ、多岐にわたっていますので、一つずつ解決をしていくということで、全体としてのガバナンスを回復していきたいと考えているところです。
- 【記者】
- ありがとうございます。2点目ですけれども、前社長の増田さんが、5年半かけて、今日まさに根岸さんがおっしゃられたようなですね、ガバナンス強化、組織風土の改善第一にと始まって、5年半注力してきて、内部通報制度も刷新して、その結果が今の状況です。そうすると、増田体制、ないしは増田さんは、どこがどう駄目だったのか、増田さんに5年半かけてできなかったものが、根岸さんになってできるようになるというのは、どういうことが、どういう理由があるからできるというふうに言えるものでしょうか。お考えお願いします。
- 【社長】
- 前任の増田のもとで、今ご指摘がありましたように、内部通報の体制ですとか、社員の声を聞く仕組みをつくったということであると思います。
その中でも、私自身、幾つかの内部通報あるいは外部通報を見ていますと、その都度、その時点で解決ができた事態も相応にあるのだろうと思っています。そういった意味で、効果が全くゼロだったということではありませんが、通報があり調査をすると、どうしても、実態が確認できたか否かといった結果になってしまう部分があります。調査の結果、実態の事実認定はできなかったという結論が出ても、明確に黒だと言えるほどの実態を確認できなかっただけの場合もあれば、本当に何も問題がなかったという場合もあります。こういった曖昧な部分が、事実認定ができなかったという枠でくくられてしまって、重要な事案が確認できていなかったのではないかと思います。このようなところは、やはり運用において足りないところがあったのではないかと思っています。
社員の声についても同様だろうと思います。声の中で取り上げるべきことがあったとしても、漏れているものがあったのではないかと思います。そういった、枠組みはできたけれども、実際の運用面について、まだまだ詰まっていないところ、不十分だったところに取り組んでいきたいと考えています。
したがって、前任の増田体制の下で、そういった枠組み作りは着実に進んできたけれども、中身としては、まだまだ是正すべき点があったと思います。その部分については、全部が全部、これまでの体制でできなかったというのではなくて、そうした取り組みの上に、私の取り組みがあるのではないかと思っております。
逆の考え方を申し上げますと、もしそうした内部通報体制やお客さまの声、社員の声を聞くような体制がなければ、これからつくっていくということで、フレームづくりに半年なり、1年かけて、そこから取り組み始めるということになりますと、さらに時間かかることになります。これは経営としては継続で行うものだと思っています。前任がやったものに積み重ね、その中で足りない部分について、一つずつ解決することによって、着実に歩みを進めていきたいと考えております。
- 【記者】
- 承知しました。関連して、内部通報で、この1年、朝日新聞で報じてきたものでいうと、顧客情報の関連で言えば、もう通報内容、資料がそろっていて、専門家が見れば違法だとするものを、日本郵便、日本郵政の社内チームは違法じゃないと言い、点呼問題でもですね、まさに自分の職場で点呼しないという通報に対して、確認できないと。本人がいわば自白しているにもかかわらずですね。こういう事例を見ていると、もう不正があっても目をつぶる通報制度なんじゃないかと、社員にもそう思われていると思うのですけど、そこはいかがでしょうか。
- 【社長】
- ご指摘の点、一つ一つの事案を見れば、やはり不十分な点があったのは、否定のしようがない事実だと思っております。ただ、一方で、幾つかの事案については、外部の専門チームの中で認定された事案もあります。今回なぜそういった事実認定に至らなかったのか。客観的な証拠にこだわり過ぎていて、いわゆる処分という意味ではできなかったとしても、事実として相当程度問題があれば、それについては何らかの対応を行うとか、そういったステップをもう少し明確にすることによって、より機能を発揮できるように見直ししていく必要があるのではないかと思います。
既にいろいろなご指摘をいただいて、着任前からも取り組んでいるところですけれども、抽象的に頑張りますと言っても改善できませんので、一個一個の具体的な中身で、それが十分な対応だったかどうなのか、一つ一つの事案を積み上げていきませんとなかなか是正できませんので、ご指摘のような事案を教訓として、一つ一つ直していきたいと考えているとこです。
- 【記者】
- あともう1点だけお願いします。前東海支社長として、先日、報酬自主返納の処分がありました。東海支社長でいらしたときに、この点呼の問題について、何か情報として接したことがあるのかどうか、あわせて、見過ごしたご自身の責任について一言お願いします。
- 【社長】
- まず、東海支社長として、支社は郵便局を管理する東海地方の責任者ですので、その責任は非常に重たいものがあると考えております。個別の事案で言いますと、東海支社の管内でも、昨年の秋くらいに点呼が未実施の事案がありました。
その時点では、ほかにないかということについて、支社の中でも確認をしましたけれども、まさにこれまでご指摘、ご説明をさせていただいていますように、点呼については基本的にやっているよね、というような感覚で支社の中でも議論していましたので、注意喚起などはしたものの、そこで終わっていたというところがあります。そういった点では、対応の仕方について不十分な点があったのは事実ですし、反省しております。
したがいまして、一つ一つの事案に基づきながら、今までの事案を反省し、いろいろなことを踏まえながら、全体のガバナンスの改善に努めていく時期だと思っております。いずれにしましても、フレームワークをつくったからそれでよしということではなく、その実態を機能させるためには、その事案を積み上げながら、私自身、その運用を学習していく必要があるのではないかと実感しているところです。
- 【記者】
- よろしくお願いいたします。成長戦略についてお伺いをします。次期中計の骨子を年内にもお示ししたいということでしたけれども、今後の成長への考え方の重点分野などですね、改めて現時点でのお考え、具体的にお伺いできればと思います。
関連して、それも言及がありましたけれども、まず足元、点呼問題への対応が優先ということでしたけれども、そういう中で、成長すべき物流事業というのが、ある種、目の前の問題に忙殺をされている中で、新しい未来への絵を描けるのかどうかってなかなか難しい局面なのだと思うのですけども、そういう中で、どう成長を模索していかれるのか、その点も含めてお聞かせください。
- 【社長】
- グループの成長戦略ということで考えますと、やはりご指摘のありました物流の分野、それから不動産の分野、ここが大きな柱になるのだろうと現時点で考えております。そのほか、郵便局の窓口を使って自治体などのいろいろな事務を受託するといったことがありますけれども、どちらかというと、成長というよりは、せっかくのネットワークを生かして、地域のお客さまの利便に立とうということで、ここでの収益の積み上げというのは、かなり限定的ではないかと見込んでおります。
その中で、物流ですけれども、一つは、トナミホールディングスの株式取得を行いましたけれども、そうした物流の分野についても、これまでのBtoCの分野から、幹線輸送という形で、少しこのウイングを広げていく、こういったところについては、今の足元の郵便局の問題とは別に取り組めるところでもあろうかと思います。
もう一つ、足元の点呼の問題とも絡みますけれども、そうは申し上げましても、全国のネットワーク、あるいは特に小型の荷物については、やはり私どものアドバンテージがありますので、これを生かさないというのは、全く経営としてはナンセンスだと思っております。
したがいまして、冒頭でともかくガバナンスを回復してと申し上げましたのは、そこが成長戦略であるからこそ、今の問題点をしっかりと早期に解決して、今申し上げましたような小型の荷物の分野について、より注力できるような体制を一刻も早く取り組む必要があるのではないかと考えています。この部分に取り組めませんと、正直、成長戦略としてはかなり厳しいというか、かなり限定的になってしまいますので、裏腹になりますけども、まずしっかりやることが、成長戦略の次のステップになるということで、冒頭申し上げた次第です。
- 【記者】
- 当然、優先順位としては点呼問題への対応というところがあるけれども、それを対応する体制を早くつくれることが、まずは一番、その成長に向けていける一番の点だと、そういう理解でよろしいですか。
- 【社長】
- もちろん、そのとおりです。ただ、幹線輸送ですとか、営業の部分についても、当然に既存のお客さまからご心配いただいて、いろいろお問い合わせをいただいているところですから、ここの部分に対してしっかり対応するとともに、オペレーションを提供することによって、守るだけではなくて、ちゃんと取り扱いが増えるようなご提案ができるような体制に早く持っていかなければいけません。しかしご指摘のとおり、ガバナンスがしっかりしていないと誰も聞いてくれないと思いますので、その順番は間違えないように、しっかり足元の問題に取り組むということが現在の重要な課題と捉えています。
- 【記者】
- 株主総会では、現場と本社の意見交換があまりきちんとなされてないのではないかって指摘するような株主の方のご発言も、幾つか似たような感じであったのですけれども、現場の意見を経営にどのような形で、今後反映していくお考えがありますでしょうか。
- 【社長】
- これだけの社員を抱えていて、各地域にネットワークがある会社、グループですので、日々お客さまに接している社員の声が非常に重要だということは認識しております。
したがって、日本郵便においてこれまで「郵便局未来会議」という形で社員と相当程度コミュニケーションを取ってきました。日本郵便だけではなく、ゆうちょ銀行、かんぽ生命の幹部も参加して意見交換をしているところです。
そのほか、本社の人間も、郵便局、あるいはゆうちょ銀行やかんぽ生命の直営店やセンターなどに足を運んでいます。いろいろな意見を聞きながら、その中で、例えばシステム面などの使い勝手が悪いとか、あるいはこういったところがお客さまニーズとしてあって、私どものやり方がずれている、といった話は、日々お客さまに接している社員の声が一番重要ですので、今申し上げたような仕組みを使いながら、経営に取り込んでいきたいと思っております。
ただ、どこまでいっても、全社員数に対しまして、本社や支社の社員数も限られていますので、全ての社員の満足ということはなかなか難しいかもしれませんが、日々、そういった機会を多くする、確保するということが重要だろうと思っております。
さらに申し上げますと、一連の金融の問題などにつきましても、地域のそれぞれの郵便局にどのような営業指導が行われているかというところも、単に任せきりにしているのではなくて、郵便局のミーティングに、支社なり本社なりの社員が積極的に入り込んで状況把握をする、あるいは悩みやとか疑問点などを解決するといったこともあろうかと思います。
一連の問題を踏まえまして、日本郵便におきましても、そうした取り組みを進めているところですので、それらをいろいろと組み合わせながら、問題点について、経営として把握をしていきたいと考えているところです。
- 【記者】
- ありがとうございます。あと、郵便局の持ち味だとか、本来の力を生かす形にしていくには、どうしても公的な業務を、ボランティアでなく、ビジネスとして展開できる形が必要になると思うのですけれども、今後も継続的に審議される郵政の関連法案の見直しに、そうした部分も期待はされていますでしょうか、上乗せ規制とかだけでなくて。
- 【社長】
- 上乗せ規制の撤廃については従来からお願いしてきたところですが、郵便局が地域のお客さまのお役に立つためには、従来のゆうちょ銀行・かんぽ生命だけではなくて、自治体からの受託というのは非常に大きな要素というか、項目だろうと思っております。
したがって、今、法案の中で、そうした業務についてちゃんと位置付けようというようなことはありますが、もちろんそうした位置付けをして、明確にしていただくことは非常にありがたいことですし、あるいはいろいろな形での地方交付税の措置だとか、こういったこともありがたいことですけれども、これに限らず、私どもとしては、きちんと自治体の皆様方に私どもが提供できるサービスをお伝えして、地域の方々に役立てる受託業務をきちんと広げていきたいと考えております。
- 【記者】
- 本当にこの収益の柱としては、先ほども物流と不動産にということをおっしゃられたのですけれども、ある部分、ユニバーサルサービス的な第4事業として、そういう公的な業務というのをこれからお考えになっていくような、将来の郵便局ネットワークを残していくために、そういうふうには考えていらっしゃいますでしょうか。
- 【社長】
- もちろん重要な柱ですので、それが4番目なのか、あるいは不動産セグメントを独立させましたので、5番目なのかというところはありますが、郵便、貯金、保険に次いでの重要な柱であることは、ご指摘のとおりです。そういった点も当然、中期経営計画を検討する中での非常に重要な要素だと考えております。
- 【記者】
- ありがとうございます。あと1点だけ、ゆうちょ銀行とかんぽ生命の持ち株比率、どんどん下がっていく中で、グループ一体感、これまでのお話、説明の中にも少し出てきたと思うのですけれども、今後さらに、どのように担保、グループ一体という感覚をどのように担保されていくお考えでしょうか。
- 【社長】
- 一つには、ようやく金利がつくような、いわば通常の状態が戻ってきましたので、今は来客誘致などまだまだ制約があり、コンプライアンスを守ることが前提ですけれども、お客さまに対して、郵便局の窓口で商品を説明する、その結果として、ゆうちょ銀行やかんぽ生命の取り扱いが増えるということになりますので、そうした形でグループが一緒にあることの効果をきちんと、実を上げていきたいと思っております。それから、これは社内で議論を始めておりますけれども、例えば広報一つ取ったとしても、せっかく日本郵便あるいはゆうちょ銀行、かんぽ生命、それぞれでいろいろな取り組みを行っているのですから、それぞれの会社だけのPRではなくて、グループ全体としてPRできるような仕組みなどを含め、グループとしての一体感が、株式の比率ということだけではなく、実際の活動として、中身として目に見えるような形で取り組んでいきたいと思っております。
各社の社長とも、グループ一体と私どもは言っておりますけれども、こんなことがグループ一体だという具体的なものをお示ししていかないと、ご理解いただけないのではないか、ということを話し始めているところです。そうした点も、中期経営計画を議論する中で、もう少し具体的にお示しできればと考えているところです。
- 【記者】
- 先日、トップメッセージの欄が更新されていて、そこの中でも社長ご自身も上場企業グループにふさわしい成長を実現していきますというふうに書かれていてですね、今、御社だとROEというのを現時点だとかなり重視していらっしゃると思うのですけれど、ただ、一方で、そもそもの中計の目標自体も、4%程度と、ちょっと市場、上場している市場、上場企業としては若干ちょっと、あまり満足されない水準かと思いますけれども、このあたり、次の中計を立てていく上では、いわゆる上場企業にふさわしい成長というのは、このROE基準にして、もっと高い、より、ないしマーケットが求めるような水準というのを出していきたいという、そういうメッセージだというふうに捉えてよろしいのでしょうか。
- 【社長】
- 結果として、いろいろと議論した結果、現実的というか、実現可能な数字という意味で、マーケットの皆様が満足できる水準かどうかというご判断はあろうかと思いますが、今ご指摘のとおり、ROEの水準というのは指標として念頭に置いて検討すべき項目だと思っております。具体的な水準をどこまで言うかというのは、中身を精査して、今後検討していきますが、ご指摘のような観点で、ROEを含めて議論していきたいと考えているところです。
- 【記者】
- わかりました。もう1点、これ、分かればで大丈夫なのですけれども、現時点で今の点呼の件というのは、業績への影響というのはまだ完全に、まだ何も分かっていることはないという理解でよろしいでしょうか。
- 【社長】
- 具体的な数字としてお示しできるまでのことについては手元にございません。ただ、いずれにしましても、委託費用の部分、それから収益の面についても影響が出てこないとも限りませんので、この点、お示しをしなければいけないような数字が出てきましたら、改めてお知らせしたいと考えております。
- 【記者】
- 先ほど来からいろいろと、ガバナンスの問題ですとか、さまざまな問題が山積していると思うのですけども、一方で、全国郵便局長会の会長も今年度から替わって、新しい体制になりました。こういう危機的な状況の中で、局長会との連携、協力、そういったことも必要ではないかと思うのですけども、そのようなことをどのようにお考えでしょうか。
- 【社長】
- いわゆる局長会というのは、部外の任意団体なので、団体と会社の施策について直接的な議論というのは、場合によってはインサイダーの話になってしまいますので、これはもちろんしにくいと思っております。
ここはしっかりと分けなければいけないと思っておりますが、一方で、お客さまと日々接しているのは郵便局ですので、そうした意味で、社員の声も同様ですけれども、郵便局長の声というのをちゃんと聞くこと、コミュニケーションを取ることは重要だと思っております。今、お話しのありました静岡の勝又郵便局長、郵便局長会の会長になりますけれども、私は東海の支社長でありましたし、そのときからよく存じ上げています。もちろん勝又局長もそうですし、それ以外の局長とも、いろいろな形で意見交換をするということは必要なことだと思っております。あくまでも会社の社内の意見交換としてですが。
ただ、一義的には、どうしても郵便局長ですので、日本郵便の中でということはあろうかと思いますけれども、私自身、日本郵便の局長、社員もそうですし、ゆうちょ銀行、かんぽ生命の社員ともいろいろな形でコミュニケーションを取っていきたいと思っておりますので、そういった意味では、危機的な状況だからこそ、フロントで働いている社員といろいろな形でコミュニケーションを取り、現実を把握することは非常に重要なことだと考えています。
- 【記者】
- まず、ガバナンスについてお伺いしたいのですけれども、個別の問題というよりは全体的な、一般的な考え方として、先ほどシステム対応であったり、モニタリングの強化であったりというところを例に挙げられたのですけれども、どういった考え方で、もう少し具体的に言うと、例えばデジタルを活用するとか、一般的に全ての問題に関連する部分として、どういった考え方でそのあたり、強化されていくのか、教えていただけますと幸いです。
- 【社長】
- これまでとの比較で申し上げますと、紙での確認、紙での記録、あるいは手作業での確認、こういったようなものがやはり多く、どうしても人がやることですので、エラーもあれば、意図的にやらない、隠そうということがあります。したがって、点呼の問題も典型的ですけど、いろいろなものをデジタル化し、ちゃんとシステム的に記録ができるということは、非常に重要な要素だろうと思っております。内部統制としてのデジタル化は、点呼だけではなくて、これを機にむしろ全般的に、見直しを進めるべきではないかと思っております。
それから、通常業務として取り組むデジタル化も必要ですが、もう一つ、やはりけん制という意味では、直接的な一線、フロントで行っている以外の、いわゆる二線、三線での機能強化も併せて行っていくということであろうかと思います。
その二線、三線という意味では、デジタル的な記録ということであれば、かなり証跡がはっきりしますけれども、ともすればこれまで形式的な確認にとどまっていたものを、実態がきちんとできているかどうかという視点で全面的につくり直す必要はあると思っています。それから、そうしたものが全体として機能している、この機能というのは、経営に対して速やかに報告できるように、内部通報から上がってきた声なども、そこで横に検証する材料になると思いますけども、そうしたことが全体として機能するように取り組んでいきたいと考えています。
- 【記者】
- ありがとうございます。すいません、ちょっと事業面でももう1点お伺いしたくて、ちょっと極端な私の理解の仕方であれば大変恐縮なのですけども、先ほど郵便窓口について、公の事業とかを引き受けて、業務拡大するにしても、利益の上積みというのはちょっと限界があるのではないかというふうなことをおっしゃっていたと私は理解したのですけれども、そのあたりにつきまして、足元で、郵便局の中でも担い手というのも減ってきていて、実際一時閉鎖というような局も目立つようになってきていて、なかなか既存の郵便局網というのを今の形のまま維持していくのは難しいのではないかというふうに考えております。足元で半日営業、半日配達であるとか、いろんな取り組みがあるとは承知しているのですけれども、言ってしまえば、その統廃合とかも含めて、今後の郵便局網の在り方など、考えていらっしゃることあれば教えてください。
- 【社長】
- 法令上の問題を言えば、過疎地についてはネットワーク水準を維持せよということになっている一方で、都市部、そこについては制約がないので、いろいろな統廃合も議論できるのではないかというご指摘は十分承知をしています。
もちろんそうした議論があることは否定しませんし、一部、個々の局を見ながら、移転をしたり、場合によっては2局を1局にしたりといったことは議論としては十分あり得ると思ってはおります。ただ、局を移転、あるいは統廃合しようと思いますと、地元の方々のご意見などがあると、かなり時間がかかるというのも事実です。ご指摘がありましたように、1日の中で、お客さまが来る時間というのはかなり閑繁の格差があります。むしろ都市部などはその閑繁の部分を、お客さまがいないところからお客さまのいるところに社員が移動することによって要員を多く配置して、お客さまにサービス提供を行うということも考えられます。昼時間帯の窓口休止程度だとなかなか効果がありませんけれども、例えば2時間、3時間、あるいは半日という単位になりますと、かなりフレキシブルに人が動くことができます。短期的には、今はまだ昼時間帯のみにとどまっていますので、なかなかその実が見えてきませんけれども、むしろそういった局間の柔軟な要員配置を加速させることのほうが、特に人手が足りないと言っている中では効果的ではないかと思っております。
この点につきましては、私自身、本来もっと数年前から議論をすべきだと、あるいは社内でも議論してきたつもりですけれども、コロナの問題、あるいはかんぽ生命の不適正問題があって、本社の中に議論がとどまってしまっていて、ようやく郵便局で実際動き始めたというのが実感です。統廃合などについてはむしろその後で、これをまず加速させて、もちろん個々にはいろいろな対応があろうかと思いますけども、全体としては数ありきで議論するよりは、まず今の施策にある程度効果が出るように、ちゃんと実を取ることをしたほうが効果的ではないかと考えているところです。
- 【記者】
- ありがとうございます。すいません、最後1点だけ、先ほどのフレキシブルな労働配置というところでいうと、労働組合のほう、JP労組か、労働組合のほうから会社側に対して、隔日での営業であるとか、郵便局も丸一日閉めてしまう、それで労働配置をちょっと見直すというような働き方ができないかというふうに協議を持ちかけているというふうな発言が以前あったのですけれども、そのあたりについて、根岸さんご自身はどんなふうにお考えになられているのか、今後そういった可能性はあるのかについてお願いします。
- 【社長】
- 私自身、この2年間、本社から離れていましたので、組合の方々と直接その議論をしていませんが、ただ、一般的に申し上げますと、もちろん一日丸々閉めてしまうということは、今後、議論は十分成り立つと思いますけれども、地域特性、特にほかの金融機関が週のうち、例えば1日2日ぐらいしか開いていないといった状況を目の当たりにしますと、それだと、利便性としては、そうでない地域と比べてかなり劣ってしまうところがあります。この点、半日ぐらいだと一日のどこかの時間帯が開いていますので、現実的なところだと思います。そういったことをした上で、どれだけ要員配置ができて、それでもやはり要員配置が難しくて、1日単位だということがあれば、そうした議論はあり得るのだろうと思いますけれども、大枠としては、段階を追っていったほうが現実的ではないかと思っています。
ただ、例えば観光地で、土曜日、日曜日を開けたいけれども、どうしても現行の人繰りの中で難しいときに、地域の商店街では、大体の商店が水曜日とか火曜日に閉めているのに郵便局だけ開けていて、土曜日、日曜日は郵便局だけ閉まっているといったことは、やはりおかしな話だと思います。そうしたことも含めて、一日単位のことを全く否定するわけではありませんけれども、各地域の実情、あるいは議論としての段階を追って進めることのほうが、現実的で、かつ効果が比較的目に見えてくるのではないかと考えているところです。
- 【記者】
- 今の質問に関連して、今のは、主に地方を想定したやりとりだと思いますけれども、都市部に関しては、賃料はじめコストが高い部分もあって、集約し得ると増田さんが4月の会見でもおっしゃっていましたけれども、都市部の集約についてはどういうお考えをお持ちでしょうか。
- 【社長】
- 私も同じ認識で、集約し得る、当然やる可能性はありますけれども、ただ、だからといって、数ありきで、何局ぐらいはできますというようなことではなくて、むしろ一つ一つの実情に合わせてだと思っています。
例えば都市部、近くに郵便局があったとしても、典型的にこの大手町とかはそうかもしれませんけども、夕方など特定の時間だけはどの局もビジネスのお客さまで混んでいるという場合、そこを統廃合したとしても、それなりに大きなスペースが必要となって、賃料もそんなに変わらないし、混雑も全然変わらないのであればあまり意味がありません。むしろ隣ではなくても、少し離れたところで、夕方手すきがあるようなところを何時間か閉めて、忙しいところにシフトさせるといったほうが、お客さまの利便性の向上にもなりますし、私どもとしても多分超勤が減少するなど、人的にも効率的になる部分もあろうかと思いますので、むしろ都市部のほうが、そうした柔軟な要員配置がしやすい部分もあります。
したがって、今の時点では統廃合ありきみたいな形で考えるよりは、その地域の中で何が一番効率的かということを考えて、いろいろな選択肢を検討すべき時期ではないかと思っております。もちろん、時間が経過すればその時期に応じて、メインになる議論は変わってくると思いますが、今、せっかくそうした柔軟な要員配置、これも本来であればもっと数年前からやるべきだと思っていましたけれども、ようやくそこが緒に就いたところですので、まずこの運用を確実に、より高度化というか、より一般化させて、効率化する中で、統廃合を考えるとしたらむしろ次のステップではないかと考えているところです。
- 【記者】
- ありがとうございます。あともう1点、ちょっと抽象的な質問になるかもしれませんが、先ほどは局長会の話もありましたけれども、その局長会も含む政治団体、あるいは局長会から要請を受けた政治家からですね、永田町に呼ばれて対応するということも、社長としてはお仕事としてあるかと思います。そういう局長会のみならず、政治の世界との向き合い方、つき合い方、ここで何か根岸さん、考えておられることあったら、スタンス教えてもらえないでしょうか。
- 【社長】
- 今でも郵政民営化法の改正法案の動きがありますように、国会議員の先生が私どもの事業に対してご関心を持っていただいていることは非常にありがたいことだと思っております。したがって、何か現状についてご質問などがありましたら、それに対して対応することについては、真摯に対応すべきだと思っております。
一方で、何かそこが特定の人への利益誘導や、あるいはそのルールを曲げてということに対しては、やはり毅然とした対応を取る必要があろうかと思います。その点につきましては、社員とのコミュニケーションと同様かもしれませんけれども、コミュニケーションはしっかり取るべきですし、しっかりと取り入れるべき意見は取り入れればいいと思いますが、何かルールを曲げるようなことについては、しっかりとした、毅然とした対応を取る、という原則をこれまでどおり続けるということに尽きると思います。
- 【記者】
- 以前に点呼の問題のときに、法律と会社が出すマニュアル、研修の間に不備があるのではないかというご指摘をさせていただいた経緯もあるのですけれども、今回、何か別のチームを立ち上げて、ほかの、点呼だけではなく、別の何か業務の中で、問題があるかもしれないというところで、再発防止に取り組むということをお聞きしたのですけれども、別のチームというのはどんなものがあって、そこはどういう活動をして、今実際どんなことになっているのか、教えていただけますか。
- 【社長】
- 日本郵便からも補足をお願いしますけれども、点呼だけではなくて、やはり手続きそのものについて、見直しをしたような手続き、あるいは不十分な手続きがあるのではないかと思っています。こういったものについては点呼問題の担当は、今の足元についてしっかりとやらせることがメインですので、日本郵便の中にそれとは別のチームを立ち上げています。その中で、特に点検項目については、社内でやや保険をかける意味で追加的に行っているような事項などもありますので、レベル感も見ながら、むしろきちんと法律で定められた事項を行うために、重要度が低い社内でのルールについてはやめるとか、こういった見直しを全体的に行う取り組みを始めているというところだろうと思います。
- 【事務方】
- 今、社長の根岸から説明したとおりですが、点呼の関係は、足元でしっかり再発防止に向けて取り組んでいく、あるいはオペレーションの確保も含めて取り組んでいく中で、チームを特設で立ち上げています。ご指摘いただいているとおり、点呼問題だけではなくほかのさまざまな業務も行っております。法令含めコンプライアンスの観点、チェックの観点も含めて大丈夫かという部分については、これもご指摘のとおり、社外取締役含めさまざまなところからご意見をいただいているところです。こういうものを網羅的にチェックしようということで、部署問わず横断的な形で、法令事項がその事業ごとにちゃんとできているのかどうかを洗い出して、チェックする取り組みを既に始めています。ここを今、点呼の問題に当たっているチームだけでやるという形ではなく、全部署横断的な形で、また、そのチェックも含めて、形骸化していないかという観点も含めて、全社的な取り組みとして、点呼のみならず、法令順守の体制が整っているのかというところについてチェックをするということで、今、日本郵便内で取り組みを進めている形です。
- 【記者】
- チーム名、何か名称はあるのですか。
- 【事務方】
- 日本郵便の経営企画部が中心になりまして、法令順守の体制ですとか、業務、あるいはマニュアル、そういったものを確認するチームをつくろうとはしておりますが、現在、その名称について具体的なものは定まっているような状況ではございません。
- 【記者】
- まだできてないということですか。
- 【事務方】
- そういう取り組み、チームをつくって進めるという方針は決まっているのですが、チームの名称について具体的に定まっているものはないという状況です。
- (※記者会見における発言および質疑応答をとりまとめたものです。その際、一部、正しい表現・情報に改めました。)