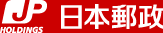- 現在位置:
- 日本郵政ホーム

-
日本郵政株式会社の社長等会見

- 2025年3月26日 水曜日 日本郵政株式会社 社長会見の内容
2025年3月26日 水曜日 日本郵政株式会社 社長会見の内容
- [会見者]
- 日本郵政株式会社 取締役兼代表執行役社長 増田 寬也
- 【社長】
- 私から2件、報告を申し上げます。まず1件目です。ローカル共創イニシアティブ第4期の実施についてです。お手元の配布資料をご覧になりながらお聞きいただきたいと思います。この取り組みでございますが、公募により選出されました日本郵政グループの社員を2年間、地域で活躍するローカルベンチャー企業や自治体に派遣するというものです。目的としては、地域における新規ビジネスなどの創出を目指すものです。2022年4月に第1期生を派遣いたしました。その後、毎年4月に派遣を行い、昨年の2024年4月に第3期生の派遣をいたしまして、このたび、第4期生として、今年の4月から新たに公募で選出をされました社員7名を、資料の中ほどのところに記載をいたしております7地域に派遣をいたしまして、活動を開始するということになりました。
本取り組みでは、これまでに計16名のグループ社員を13地域15組織に派遣し、現地関係者とともに新規ビジネス創出に向けた調整を行いまして、第2期については来週3月31日で2年間の派遣期間を終了することになっています。
具体的な成果はいろいろございますけれども、例えば、「ゆうパック」と新幹線を活用して行う荷物輸送サービス「はこビュン」を連携して、地方の農産物を輸送する実証実験や、NFTを活用した実証実験を開始したところです。そのほかにもいろいろございますが、最近では、そのようなことをやっております。NFTプロジェクトについては、本日、お知らせをウェブサイトに掲載しておりますけれども、4月3日から石見銀山地域においてデジタルスタンプラリーを開始することといたしました。このように、派遣者を起点に、派遣先企業の知恵と郵便局を活用した共創事業が生まれてきているところです。このほかにも、第2期、第3期の派遣を起点に、具体化を進めている企画もございますので、具体的な形になり次第、今後も随時公表していきたいと思います。
当グループは、新たな分野でのこのような取り組みを積極的かつ主体的に行うことによって、持続可能な地域社会づくりに貢献していく新たな役割を模索してまいります。
2件目です。こちらも配布資料がございます。日本郵政・ゆうちょ銀行・防災科学技術研究所による防災情報の利活用などに係る連携に関する協定の締結についてです。今申し上げました3機関で協定を締結し、今後の自然災害に対しての対応に取り組んでいこうということです。当グループでも、平素から自然災害が発生した場合に備えた役員や社員の訓練など、危機管理体制の整備に取り組んでいるところです。特に間近での発生確率が高いと言われております首都直下地震、そして南海トラフ地震など、大規模災害の発災が危惧をされる中で、当グループが社会から求められるサービス、これは極めてインフラ的に重要なサービスでありますので、これを極力可能な限り継続していくということが必要になります。当グループとしてもさらなる災害対応力の向上が必要と考えております。そこで、日本郵政およびゆうちょ銀行が防災科学技術研究所の持つ先進的な情報を活用して災害対応力の向上を図るために、防災情報の利活用などに係る連携に関する協定を締結いたしました。具体的な協定内容としましては、自然災害に係る防災情報の利活用がございます。
現在、内閣府防災が構築中の防災デシタルプラットフォームの中核を担っております新総合防災情報システムというものがございます。このシステムに防災科学技術研究所のノウハウを集結した基盤的防災情報流通ネットワークが活用されております。配布資料の別紙にそのあたりの関係をポンチ絵で描いてございますのでそれをご覧いただければと思います。この基盤的な防災情報流通ネットワーク、ポンチ絵の真ん中のところに描かれております「SIP4D」というものでございますが、このネットワークには、地震や台風などの直接的な災害情報に加えまして、平時から災害対応に必要とされる多様な防災情報が収集されているものです。今後、このネットワークを郵便局ネットワークの事業継続のためにも活用させていただきたいと考えておりまして、こうした取り組みを通じて、自然災害に強い持続可能な地域社会の実現に向けた取り組みも行ってまいりたいと考えております。
さらに、当グループが郵便局ネットワークで把握した地域の被災情報などを防災科学技術研究所に連携をして、地域社会全体の災害対応力向上に貢献するということも、今後検討していくこととしております。この協定締結をきっかけに、当グループは、今まで以上に自然災害に強い郵便局ネットワークを構築し、地域の皆さまの安心・安全の拠点として地域防災に貢献していきたいと考えております。
なお、裏面の別紙、協定のイメージのところをご覧いただくとお分かりのとおり、郵便局を所管しております日本郵便は、もう既に指定公共機関に指定をされておりますので、内閣府の新総合防災情報システムにつながっております。当社とゆうちょ銀行が加わってさらに拡大をさせていくということになります。なお、かんぽ生命については、ここに加わることについて今検討中と聞いております。いずれにしても、グループ全体として防災対応力を向上させる、そして地域にその力を裨益させていくと、こういうことを狙っているものです。
私からは以上の2件でございます。
- 【記者】
- 質問2問、お願いいたします。まず1問目なのですけれど、先日、日本郵便がゆうちょ銀行の顧客情報を営業目的に不正利用していた問題について、詳細と処分と再発防止策を公表されました。今後、再発防止策と、あと原因にも挙げられていた組織風土の改善に向けて、どのように取り組んでいくお考えかお願いいたします。
- 【社長】
- まず初めに、今ご指摘いただきました顧客情報の不正流用の問題を引き起しましたことに対しまして、改めておわびを申し上げたいと思います。このような事案が発生したということを厳粛に受け止めまして、経営責任を明確化するということで、役員の処分を発表したところでございますが、今後の対応、確実な実行が大変重要だと考えております。この問題、先般の発表の中でも記載してございますが、主としての原因は四つあると思います。営業推進を優先してきているということで、数字での競争意識が強い、そして、リスク認識がまだまだ不十分であり、さらには、ガバナンスが未成熟、不十分なことにより統制機能が十分に働いていないということです。それらはまさに主因に該当しますが、さらに当グループが保有している多くの個人情報のずさんな取り扱いがこの背景にあったと痛感をしております。
個人情報の扱いは年々非常にレベルを高くして対応していかなければいけないと感じております。5年、10年前とは、はるかにレベル感が違ってきていると思いますが、この個人情報の扱いを、フロント社員の一人一人まで徹底していくということが、極めて不十分であり、ずさんであったということが、その背景にあったのだろうと思っております。
かんぽ生命の保険商品やあるいはゆうちょ銀行の投信など、お客さまにいろいろ商品をお勧めするときは、当然のことながら情報を使うことに同意をしていただいているお客さまに限り商品を提案するということは大前提で、ほぼ徹底をされてきていると思います。しかし、お客さまに郵便局に来局していただいて商品を提案するにあたって、同意を取るよりも前の段階、来局を誘致する段階で情報を不正に使ってしまっている。来局誘致のためにお客さまの情報をリスト化する段階でも同意をいただいていなければ違法という厳密さが十分に伝わっていなかった。
ほかの場面もいろいろあると思いますが、基本的なことについて、しっかりと社員全員に徹底をさせることが不十分だったと思っております。特にグループの統制が不十分と痛感しておりまして、第1線のみならず、第2線の部署、いわゆるコンプライアンス部門については、完全にアウトとは言い切れないグレーな部分のところについての統制も不十分で、この2線の権限をもっと強化しなければいけないと考えておりまして、こういった対応・取り組みを行いますということを金融庁、それから総務省にも届出をしております。あとは再発防止策を確実に実行していくということが必要になりますので、今後それをさらに繰り返しフロント社員の皆さん方にもお伝えをして、組織風土として根づくまで取り組んでいきたいと思っているところであります。
- 【記者】
- もう1問、質問させていただきます。郵政民営化法の改正について、改正案を自民党が議員立法で今国会への提出を目指しています。その配当を活用して、交付金拡充とか、自治体の窓口業務受託の本来業務化とか、郵便局ネットワークの維持の支援というのが柱になっているわけですけれども、一方で、この改正案が完全民営化を目指した当初の法律に逆行するという批判もあります。今後の郵便局ネットワークの在り方も含めて、改正案についてのご所見をお願いいたします。
- 【社長】
- 自民党のほうで、今お話ございましたような郵政に関する法律について、議員立法として改正案を検討中ということは承知しておりまして、私どもも非公式の場で、意見を聞かれたこともございます。
当グループとしての考え方ですけども、基本的には立法府でお決めになる、こういう仕組みというのは最大限尊重をしなければいけないと思っております。今の当グループが存在をしている、民営化をされるというのも、国民全体を巻き込んだ大変かんかんがくがくの議論の中で決まった話でございますので、今回も立法府がどのような体制がいいのかという判断をしたのであれば、それは最大限尊重しようというのがまず基本です。その上で、この民営化が行われて、現行の体制の中で特に金融2社が業務を行うときに、一般的な会社法や業法の規制にプラスする上乗せ規制が民営化法で定められております。
したがいまして、私どもとしては、法律改正が行われるのであれば、それは立法府の意思として最大限尊重しますが、もし、その中で上乗せ規制の緩和について整合的に盛り込まれることが可能であれば、ぜひ緩和をして、当グループとしての金融2社のさまざまな業務、企業価値向上が実現しやすくなるような、そんなお願いを非公式の場などでも申し上げたことがございます。
ご質問いただいたようにいろいろなものを盛り込まれるお考えがあるようなので、まだまだ党内で議論をされているということでもございますし、先ほど立法府と申し上げましたけれども、自民党のみならず、これまでも上乗せ規制も含めた民営化法については、民主党政権になったときにも改正が行われてきており、与党、野党共同していろいろと改正を行われたという経緯もありますので、今回、国会、立法府全体としてどのような意思でやられるかというのはまだこれからということになろうかと思います。基本は、今申し上げましたような、上乗せ規制のところの緩和がより進められるようなことが入りますと、私どもとしても、企業活動がしやすいと思っているところであります。
- 【記者】
- 同じように2点お願いします。1件ずつお願いできればと思います。1点目は先ほどおわびをされたその不祥事の件なのですけれども、増田さんがそもそも5年前、5年余り前に就任したときも、こういったコンプライアンスの徹底ですとか、組織風土の改善といったものが一番の経営課題だったと思いますが、5年たってそこはどう改善したのか、5年たってこの顧客情報の問題に加えて、不適切な点呼の問題ですとか、それから、少し前には「ゆうパック」の委託業者らへの不当な違約金の件も出てきました。いずれも法令違反が問われて、法令違反に当たる事例だと思います。こういうものが続出していることについてどう考えているか、1点目、お願いできますか。
- 【社長】
- 5年前、私が就任したのもイレギュラーな経緯でございまして、かんぽ生命を中心に発生した大きな不正問題がきっかけで、経営陣が交代した際に、入ってきたということでございました。今回の問題は、その時とは異なりますが、やはりお客さま本位で会社が活動し、成長を遂げていくことがまだまだ不十分であるものだと思います。いろいろな組織を私もこれまで経験してきましたけれども、何か一つ大きな問題を乗り越えると、必ずまた次の問題が出てきてしまいます。こういった問題は本当に常に予断なく取り組まなければいけないと思います。
先ほどお話ございました点呼の問題、これは国土交通省の管轄で、協力会社様に対しての不当な違約金については公正取引委員会から指摘されています。これらはもう明らかな法令違反です。特に点呼の関係では、酒酔いの運転があったにもかかわらず、それに対しての十分な危機感と、点呼の徹底が行われなかった。点呼記録簿にサインはあったものの点呼自体が十分徹底されなかったという、大きなミスがありましたので、これはもう何の言い訳もできない問題だろうと思います。
グループとしてコンプライアンスとか、お客さま本意を掲げておりますが、情報流用のほうは元々一つの国営事業でやっていたものが公社、それから民営化で、分社化することで全く別会社になったという経緯もあります。別企業であり、個人情報の取り扱いが年々センシティブで厳しくなっているということに全く追いついていなかったということですので、この5年間の間でも私も含め経営陣全員が、考えが及ばないというか、努力が全く及んでない部分で、フロントでの対応がちゃんとされていないということは、これはまさに統制が十分届いていないということだったかと思います。
今後は、新たなやり方で正していく必要があります。これまでも当グループは、私が就任してからも、ゆうちょも含めて常に大小いろいろ問題が起きていますが、こうした問題が起きた段階でできるだけ早く機敏に対応していかなければいけないと思います。特に今回の事案は大きな問題だと思っています。
さらに言えば、個人情報のクロスセル使用に同意をしてくださったお客さまに営業を行うのを基本として、同意取得件数はまだそれほど多くありませんので、同意を得る取り組みをもっと拡大し、顧客基盤を作り直していかなければいけないのですが、それまでの間はどうしていくのかという問題があります。同意いただいた方をベースに顧客基盤を拡大していくまでの間、今回のようなことが起こらないように、それぞれ対策をとっていく必要があり、頭を切り替えていかないといけないと思っています。
点呼とか違約金のほうは、もう本当にお恥ずかしい話ですが、初動動作の話だと思います。日本郵便の中ではちゃんと、これまでもこういう問題に対応するということが、体制としては取り組まれていたのだと思います。日本郵便の中で本来完結しなければいけない問題だと思いますが、極めて重大な違反でもありますので、これはやはり持株会社としても、もっと中に入り込んで、日本郵便の取り組みを、本当に世の中のレベルに達するまで見ていかなければいけません。こういう類いの問題だと思っています。
いずれにしても本当に基本的な動作の話で、当然やられていてしかるべきという問題でございますし、もう一度こういった法令違反を起こしたことについて、法律で決められていることの原点に立ち返って、改めて取り組みをしていかなければいけないと思います。深刻な点呼の問題については、いろいろやったことを記載する台帳などがあるのですが、どうもそれを不実記載というか、しっかりと正しくは記載してなかったところもあるようで、今調べています。
そのようなことであれば、かなりいろいろな場面を疑ってかからないと駄目な場合もこれから出てくると思っていますが、いずれにしても、この特に個別の、法令違反のところは、また調査し、その上で対応策をグループ全体としてしっかりと考えていきたいと思います。グループで起こったことですので、どんな形であれ、持株会社には何らかの形で責任がある話ですので、これについてもしっかりと見ていきたいと思います。
- 【記者】
- 今の1点目に関してもう1点、増田さん就任当初、バッドニュースファーストと言われて、悪い兆候ですとか、早く知らせてくれと呼びかけて、1年目は相当細かい不祥事もいろいろ、公表されていたような印象がありますけれども、そういった当時の何ていうか思いとか、状況、求めたことが5年たって緩んできたとかいうことはないでしょうか。今日取り上げた不祥事も外部からの指摘とか、そういうことで表沙汰になってきたことが多いように見受けますので、その点ちょっともう少しお願いします。
- 【社長】
- まず、例えば点呼の話も関西のある地元紙が報道されて、それから、全国紙で報道されたということです。全国紙で報道されたときにこちらにも報告が来ましたが、個別のある旧集配センターの事案だろうと思っていました。ただ、しっかりと調査をするということでしたので、その状況を最初は見ておりましたが、どうも非常に広がっているということで、すぐ全国調査という形になりました。やはりこれで一番深刻だと思うのは、先ほどお話にございましたが、酒酔い運転の個別事案がありまして、これはレベル感で言うと、やはりこれは公表事案だと思います。現在、それを日本郵便に指摘して、基準を変えてもらっているところです。
郵便の機材で検査していますので、警察とは少し違うかもしれませんが、少なくとも郵便の機材で呼気1リットル中0.63mgの数値が出ていました。酒気帯びは、昔は0.25mgでしたが、今は0.15mgです。酒気帯びではなくてこれは完全に酒酔いの数値ですから、なぜ即刻警察に連絡しなかったのかなどいろいろ思うところはございます。これまで、業務用の車両で、このようなことは、基本的にはなかったということのようですが、逆に、誰が見ても分かることですので、これは直ちに警察に連絡をすべきと思います。点呼の問題も数年前から不十分だったところが多いようですが、もっと積極的な対応ができたのではないかと思っています。もう言い訳もできないレベルですし、緩んでいるのか、もともとそういうものなのか、そこのレベル感は分かりませんけれども、ただ起きていることについてはしっかりと対応する必要があります。業務上のものについては警察にすぐ通報する、それから事案を公表する、処分も厳格にすぐ行うということを今後取り組んでもらうということであります。非常に対応が緩い、遅い、これを今回のことを契機に直す必要があります。また、ずっと長続きさせなければいけません。それをしっかりと確認できるような、カメラなども使って、やっていくということ。要するに約3,200カ所集配を行っている郵便局がありますけれども、今までは、点呼の様子を記録できるような状況になっていなかったということですが、点呼の実施場所をカメラのある場所に移して、そこで行うようにするということで、事後検証ができるように切り替えるよう今取り組んでいると思います。とにかく、今後は絶対起こさないようにしていきたいと思います。日々、毎日、朝昼晩行われている話なので、完全に徹底しているのか、長続きしているのか、さまざまな機材も使って点検をしていきたいと思います。
- 【記者】
- ごく簡単でいいのですけれども、不正とか不正の兆候に対する自浄能力っていうのがあまり高まってないって言えるのでしょうか。
- 【社長】
- 違約金の問題については、公正取引委員会から昨年の6月に指摘されているのですが、「勧告」にならなかったので少しほっとしていたのかもしれません。ご指摘のとおりサインはあったわけですから、もっと適切な対応が取れていたと思います。ですので、そこの危機感度というか、リスク感度は極めて低かったと、残念ながらそう思います。それも含めて、しっかりと持株会社も含め対応していかなければいけないと思っています。
- 【記者】
- ありがとうございました。長くなって恐縮です。2点目、法改正、先ほど質問に出た法改正の件でもう1点お願いします。この法改正の案の中には、日本郵便の郵便局網に対して財政支援をすることも盛り込まれていて、年650億円規模になるのではないかと想定されていますが、今日、質問に出ているように、これだけ不祥事が起きている状態の日本郵便に対して、財政支援、受ける妥当性というのがあるのかどうか、見解をお願いします。
- 【社長】
- その関係は、私どもではお答えする立場にありません。最終的には立法府が財政支援を行うということであれば、おそらく予算の中で何らかの手当をしなければいけません。国庫納付している配当金について、政府のほうで仕組みを切り替えるということが言われておりますが、そこは立法府や政府がご判断をされるのではないかと思います。
- 【記者】
- 3月15日に長野県で石破総理と伊東地方創生大臣、あと阿部県知事と昼食をされたという報道を見たのですけれども、そこでどのようなことを話し合われたのでしょうか。多分、地方創生大臣が行かれているということは、地方創生関連なのかなと想像するのですけれども、増田社長様が、消滅自治体を発表されたのが2014年だと思いますので、11年が経過する中で、当初の発表ですと、523自治体が消滅していくだろうということを書かれてらっしゃると思うのですけれども、そのときから日本全体が状況的に改善されている方向に向かっているのか、もしされていないとしたら、改善に向けて、郵便局を地方創生に向けてもっとどのように活用されていくといいか、今お感じになられていますでしょうか。実際に、もちろん今までも活用されてこられたと思うのですけれども、それの成果と、特に今後、どういうことに力を入れていかれたいとか、そのあたりのお考えをお願いいたします。
- 【社長】
- まず、3月15日のお昼の話ですが、今お話があったように、お昼を食べた後、新しい地方創生本部で設けている有識者会議を長野県伊那市で行ったので、その前に、総理もそこで食事をして、そのまま有識者会議に参加をしたという流れになっています。地方創生の有識者会議ですので、霞が関でやらずに必ず地方でやろうということで、私も土日のときにしか行けませんので、今、1月、2月、3月と土曜日に必ず地方でやっているということになりますが、会議はオープンでやっていますので、そこでの話は地域で地方創生活動をされている方たちから困難な点だとか、進めてほしい点などを伺っております。その前段のお昼のときに、阿部知事などから、シカなどが芽を食べてしまうので、獣害として非常にやっかい扱いされているのですが、ジビエを地元の特産としてやっているといったお話を聞いたりしました。総理ご自身もジビエの議員連盟(鳥獣食肉利用活用推進議員連盟)の会長をやっておられるようで、そういう地元の工夫をいろいろとその場で総理や有識者の方が聞いておられました。
私からも、ドローンを当グループで今後、業務に活用しようと思っていますが、なかなか法規制が強いため、レベル4に対応する機体で実証も行ってはいるものの、なかなか実用化は難しいということ、当然、住民の安全第一なのですが、山の中のそういう危険性のないところについてのドローン規制については、もっとやりやすいようにできないかというようなことをお話しました。もちろん、総理ですから、明確にそのことについて、その場でどうこうということではないですけど、大変興味深く聞いておられたと思います。私は、一つの例えとして申し上げましたが、そういったことがあちこちで可能になるのであれば、今、過疎地域でご承知のとおり、一部の新聞は輸送が、郵便に任されております。第三種郵便が多いのですが、どうしても朝刊が午後か夕方にならないとなかなか届かない地域がどんどん増えてきています。しかし、ドローンをうまく使うと、朝刊をより早く読めるようになっていくので、そういったことが劇的に変わるなんていう話を申し上げたところであります。
あと、地方創生の話とか人口の話もございましたが、残念ながら、この10年、地方創生ということで政府全体も取り組まれていますけれども、人口減はより加速をしています。国立社会保障・人口問題研究所の当初の推定よりも加速をしていますし、それから出生数の予測も2023年の中位推計よりも、もっとずっと悪い方向に、コロナ後も回復していませんので、もっと減る方向に向かっているということもありますので、その中で郵便局について、年金を受け取る場所ということだけではなく、地方創生の全部というわけにはなかなかいかないと思いますが、地方創生の観点から活用できる部分はあると思い、そういう話を地方創生の中でも、私から申し上げております。
郵便局の利活用については、総務省にも随分お願いしていたのですが、今、審議されている政府予算の中で、買い物支援とか、そういった郵便局での生活支援部分について自治体が特別交付税を使い経費が出せるようになっていますし、先ほど、本日の発表で申し上げましたローカル共創イニシアティブについても、ゆくゆく当グループで地方創生にもっと知見のある人間を増やそうということで行われている分野でもあります。今のうちにそういった仕掛けをつくっておいて、今後、郵便局も含めて地域の資産と申しますか、過疎地域などでは、役場以外の事業体がほとんど撤退しており、郵便局ぐらいしか残っていないところがあります。そういった地域は郵便局への期待が非常に大きいので、全部が全部というわけにはいかないと思いますが、ぜひ私どもとしても積極的に郵便局を地方創生の一つの仕掛けとして使っていきたいと考えています。今はそういう事例をいろいろ勉強している状況です。
- 【記者】
- ありがとうございます。今のお話の中で、山間地とか、朝刊を、一般紙の朝刊を配布するのに、例えば郵便局長とか、の方とか、そういうことをやってもらうとか、そんな案というのはあるのですかね。
- 【社長】
- 今の配送ルートだと相当時間がかかりますので、多くは地元紙だと思いますが、地元の新聞社では、配送ネットワークの構築が難しいので、そういう中山間地域については郵便に依頼が来るわけですけれども、印刷が夜中というか、明け方に近い時間に出来上がったものを届けるのは、今の仕組みでいえば、どうしてもその日といっても夕方になってしまいます。ただ、それをある程度の規模感がないとだめですが、ほかの郵便なども含めて、一挙にドローンなどを使って配送することできれば、組み方によってはもっと早く配送できるところも出て来るのではないかと思います。どこかの具体例を念頭に置いて言ったわけではありませんが、一つの分かりやすい例として、朝刊を午前中に読めるようにすることも、ドローンをうまく使うことによっては可能になるということ、それくらいドローンの活用は、これから日本全体の中山間の中で重要ですということを総理に申し上げました。同じような話で、そのときの出席者の方が、長野県は山小屋が多くて、大小合わせて2,000棟ぐらいあると仰ってましたが、山小屋にものを届けるというのは、ヘリでやるといろいろな規制が大きいので、ドローンでやるのが非常に有効なのだそうです。山の上ですから、地上に人がいませんので有効なのですが、今のところ、少しばかり規制がクリアできないとのことでした。そんなことも考えていくと、いろいろ組み合わせすると、中山間、へき地の輸送もいろいろ変わり得るのだろうと思っています。
- 【記者】
- あともう一点、すみません。今日発表された日本郵政様とゆうちょ銀行様と、防災協定なのですけれども、昨年、日本郵便様と気象庁が締結をされたと思うのですけれども、それとの連動みたいなところというのは何かあるのでしょうか。
- 【社長】
- 先ほどご説明しましたが、日本郵便はその仕組み全体の中にもう既に入っております。
先ほどの発表資料の別紙に「SIP4D」と書いてあるのですが、そこで結ばれている、左上のほうの「指定公共機関等」に日本郵便は入っております。コンビニのローソン様とか、セブン様などもここに入っております。そのため、もう既に日本郵便とは連携されているということになります。
- 【記者】
- 先ほどお話にもあった不適切な点呼の問題についてお伺いします。増田さんからもお話あった酒酔い運転の事案について、先ほど、直ちに警察へ報告することが必要であったというようにおっしゃっていたと思いますけれども、実際に警察への報告というのは、事案の発覚日から11日後だったと。これについてなんですけれども、警察への報告がこれだけ遅れた理由についてお伺いできますでしょうか。
- 【社長】
- その間、いろいろ調査をしていたというのが、当時の南関東支社と、それから戸塚郵便局の当事者たちの話だと思うのですが、多分、こういう事案をどう処理するかということを、しっかりとさまざまな場面で現場に徹底していなかったということが、11日後になった原因だと思います。電話連絡を入れたという情報もあるらしいのですが、とにかく話をしたのは11日後ですから、本来、すぐに警察に報告するルールがきちんと意識されてなかったということに尽きるのだと思います。
- 【記者】
- 増田さんご自身は、この件について、いつ、どのような形でこのことを知ったのでしょうか。
- 【社長】
- 私が知ったのは、今年の3月です。先ほどこういったものは公表案件だと申し上げましたが、やはり重大な案件は公表すべきです。こういった案件は持株会社のほうにも報告が来ますが、個別の事案は、基本的には日本郵便という会社の中で処理をされるので、よほど重大な事件でなければ、持株会社には報告はきません。
それはそれでいいと思うのですが、やはりこれだけ重大な事案は、公表すべきですし、報告があってしかるべきと思います。点呼が不十分だということで全国調査をするといったときに、私は、点呼を十分していないことによって例えば事故が起きたとか、重大な事案につながる点呼漏れがなかったのかと聞いたときに、事故はないものの、非常にまずい重大事案があると聞きました。
- 【記者】
- 増田さん、日本郵政という立場だけでなくて、日本郵便の取締役として、も、この事案について、ことしの3月に報告受けたという、この報告の時期については、問題はないとお考えでしょうか。
- 【社長】
- 遅いと思います。
- 【記者】
- 本来であれば、いつどのような形で報告を受けるべきだと思いますか。
- 【社長】
- 発生したときに、公表して、公表事案は当然取締役にも報告するというのがルールだと思います。
- 【記者】
- 今回この事案について、日本郵便としても公表はしていませんでした。これは、公表は不要と判断した理由は。
- 【社長】
- 今までのルールだと、公表事案には当たらないというのが解釈のようなのですが、警察に通報をするという時点で重大な事案ということで読めなくもないような気もします。詳しくは分かりませんが、やはりここまでの案件であり、しかも業務用車両ですから、公表すべきだと思います。そうすれば当然、取締役にも報告されますので。去年の5月のタイミングで公表していればそれらが全部できたと思います。
- 【記者】
- この不適切な点呼については、その後、近畿支社管内でも、かなりの不適切な点呼が横行しているというようなことが日本郵便としての調査でも分かってきたということで、ただ、一方で、今回、複数の近畿支社管内以外の、複数の郵便局でも点呼が未実施であったり、あるいは先ほども不実記載のお話ありましたけれども、その記録簿自体が偽造されているようなケースをわれわれとしても取材で確認をして、報道もしています。この不適切な点呼について、今年の3月11日に日本郵便が会見して、公表はした形にはなりましたけれども、われわれの取材ではその11日当日も、点呼が実施されていなかった郵便局もあったと取材で把握をしています。今回そういう意味では一地域、エリアの郵便局の問題だけではなくて、こういう一連の動きを踏まえると、組織全体のガバナンスの問題のようにも思うのですけれども、増田さんとして、その日本郵便の貨物運送事業者の取締役としても、責任としてはどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。
- 【社長】
- 今、全国調査をして、近畿以外の地域でもあるであろうと思っています。おそらく、全国調査が来週に終わって、それをまとめる中で、調査した内容を細かく、またさらに調べないとだめなものもあると思いますので、本当にしっかりと点呼が行われていたのかどうか、一定期間さかのぼって、カメラを確認したりするなどあると思うのですが、ただ、4月中旬ぐらいまでにそれをちゃんと全部公表するということで、取り組んでもらっていますので、どう広がっているのかなど、実態を見た上で、会社としてのガバナンスの立て直しをしていかなければいけないと思います。
ただ、この問題については、集配を担当している社員は今日も含めて、毎日外へ出て、外で活動しています。毎日朝、昼、午後と帰ってきたとき、点呼は常に行われなければいけないので、常にそれがしっかりと行われているかどうかは、日々の問題です。どういう事案を御社が把握されているか分かりませんけれども、完全に行われていること、きちんと法令にのっとった形で行われていることを期待したいと思いますが、いずれにしてもそれは日々確認しておかないといけないと思いますし、今後もそれがずっと持続的に続くよう、最後はカメラなどを使って確認する必要があると思います。さきほどの不実記載の問題もありますので、カメラがあるところで点呼を実施するということを当面は行う必要があると思いますが、それを徹底するということで、調査結果に基づくその後の対応策を実施するまでの期間は乗り切りたいと思います。
- 【記者】
- 公表のその4月中旬というのは国土交通省への報告も同じですか。
- 【社長】
- 国土交通省への報告と同時に、やはり報道機関への公表をそのくらいを目途で、しっかりとやっていきたいと、日本郵便と話をしています。
日本郵便の取締役の立場で言えば、そのくらいのスピードでやらないと、それでも遅いぐらいかもしれませんが、そのぐらいでやらないといけないと思うので、昨日、取締役会もありましたが、とにかくできるだけ早くこの問題に取り組んでもらおうと思っています。
- 【記者】
- 結果次第では、国土交通省による処分があると思うのですけれども、これ今もちろん、全国調査はまだ調査中ということでありますけれども、現状の段階で、国土交通省のその後の処分による影響についてはどのような見通しを。
- 【社長】
- 通常ですと、それはそのときにということであります。あえて言えば、どういう形の処分であれ、例えば隣接する郵便局でお客さまの荷物をカバーするとか、とにかくお客さまにご迷惑をおかけしないように取り組むということになると思います。
- 【記者】
- 分かりました。別件で違約金についてお伺いします。前回の会見、2月の会見で、増田さんが、公正取引委員会が下請法違反の認定をしたのと同様の事案がないか、対象事業者に、まさにお聞きしているということでおっしゃっておりました。もしそうした事案があればおっしゃってくださいというような形で調査をしていると。この調査の結果、あるいは進捗について教えていただけますでしょうか。
- 【社長】
- 協力会社様との間で各郵便局が交わしているのは、全体で5,300~5,400件弱の契約だと思いますが、今週の初めで97%の契約はもう既に終了したと聞いております。それらについては4月以降、スムーズに実施できるとのことです。まだ3%分ぐらい、ですから、百数十契約、やりとりを相手の協力会社様と行っていると聞いております。
それから、関東の郵便局ですが、昨年問題になったときに返金を行った事例があったのですが、返金に至るような深刻な事案は、今の段階ではないと聞いております。まだ今、協議中と聞いておりますので、その内容について私はまだ報告を受けておりません。4月になると全体が分かると思います。
- 【記者】
- これについても結果については公表される。
- 【社長】
- 今回は公表することを考えておりますが、ただ、何かいろいろ特異な問題があればそれも含めて考えます。
- 【記者】
- これわれわれの取材では、この関東の、事例とは別に、ほかの郵便局と比べて、高額で不当な形で違約金が徴収されたと主張、訴えていらっしゃる方もいます。そういう中で、今回、現状97%調査しても、同様の違反のような事案がないということなのですけれども、これ具体的にそういう同じような事案があるのかどうかということを確認する調査の手法をもう少し詳しく伺えますか。
- 【社長】
- 調査の手法は、1月20日から開始した価格協議において、協議終了後に協力会社様に、日本郵便の契約の担当の部署、日本郵便から聞いている限りは、本社から協力会社様にEメールで送付だと思いますが、調査票に自由記載の欄をつくって、何か問題になるようなことが、これまであったのかどうかを書いていただくということで、聞き取りアンケートをかけているということです。
- 【事務方】
- 全ての協力会社様にアンケート形式で、違約金の問題も含めてご意見、ご要望、あるいはご指南も含めて全て頂戴してございます。
- 【社長】
- 違約金の問題のみならず、ほかのことも含めておっしゃってくださいという、そういう聞き方をしております。
- 【記者】
- 細かいですけど、自由記述欄のところに、違約金のことも含めてというふうな文言が入っているのでしょうか。
- 【事務方】
- 違約金についても何か、ご指摘などあればという形で、広くご意見を賜っている形でございます。
- 【記者】
- そのアンケートをもとにヒアリングとかも実施されているのですか。
- 【事務方】
- その中で、もし不当な違約金の徴収が疑われるものが出ましたら、支社などを通じて、事実関係の確認を行い、そして、実際にそういったものが出れば、当然返金対応などを行ってまいります。現時点ではそのアンケートの中で、不当な違約金の徴収に該当するような事例については出ていないという状況でございます。
- 【記者】
- すいません、3点あるのですけれども、簡単な質問になるのでよろしくお願いします。先ほど、かんぽの問題もしかり、点呼問題もしかり、要するにいわゆる営業重視、営業成績重視を率先したり、配達点呼に関しても、要するに午前中に配達しなくちゃいけないという、要するに目的意識、そっちのほうが先走ってしまって、法律を守らないということが起きたと思うのですけれども、これって増田さんから見てちょっとお伺いしたのですが、これは例えば1件とか2件とかじゃないので、この下地が一体何があるのかということなのですけども、そもそも彼らは法律を知らないのか、それとも法律を後回しにする、つまり法律を守らなくてもいいと思っているのか、それはまずどちらだと思いますか。
- 【社長】
- 全部の事例が法律を知らない、あるいは法律を守らなくてもいいのだと思っていると決めつけはできないので、多分、両方交ざっているのかもしれませんが、ただ、結果からすると、例えば個人情報の保護については、非常に年々、その厳格さが上がってきているのは間違いないと思います。
昔は地方の郵便局長は、いろいろなお客さまのいろんな情報が頭の中に入っていた訳です。頭の中で全部切り分けるにはいかないのですが、それでも観念的にはやはり頭の中に入っているものであっても、ゆうちょの貯金情報を営業に使うのは、それはよくないということで切り分けるようにしていて、それはそれぞれの局長なり、郵便局の社員のある種、判断に委ねているということはあります。
しかしながら、そこまでやらないと、多分個人情報の保護が今のご時世だと徹底されないということだと思いますので、私どもから見るとこれを現場に、社員の皆さん一人一人に理解してもらうのは非常に難しい時代になってきていると思うのですが、それをやらないと企業として信用が得られないということだと思います。営業重視を切り替えるということであれば、これは会社の姿勢で直るのですが、やはりそこまでの個人情報の保護の徹底が求められるというところ、あるいは現場の方、そこまでのところをまだまだご存じない方がいるので、それを私どもはしっかりと理解するまで繰り返し教えていかなくてはいけないと思います。今のご質問に対しては両方交ざっていると思うのですが、いずれにしても、正していかなければいけないということかと思います。
- 【記者】
- ありがとうございます。ちょっと今の質問、ちょっと回答で関連してなんですけども、これ個人情報の扱いが、まだ浸透、なかなか理解がまだ深まってない状況の中で、要するに、その自治体の業務って受託できるのですかね、要するに個人情報かなり扱うわけですよね、それは可能だと。
- 【社長】
- 法律上、事務受託とかいろいろな手続きを取れば可能なことになっているので、それで、これはもう自治体と私どもとのお話ということになりますが、当然、自治体のそういう業務を扱うときには、決められたルールは守らなくてはいけません。それが守られ、しっかりと行える範囲の中でということになります。ご承知のとおり、個別で法律が全部決められているので、要件は全部満たさないとだめだと思います。
- 【記者】
- すいません、かんぽの問題なのですけども、2019年のかんぽ問題と今回の主因というのは全く変わらないような気がするのですけれども、そのときから、要するに結局何も改善していないのではないかというふうな思いもあるのですが、その分はどう。
- 【社長】
- ご指摘されて、あえて反論することもないですし、現実に不正事案が起こっていますので、そういう今ご指摘いただいたことが今後ないように、これからしっかりやっていきたいということです。今の時代、求められるところのレベルが非常に高くなっていますので、それにしっかりとついていかないといけません。
損保業界もそうですし、それから生保の業界でもいろいろ代理店を使いながら業務を行う場合に、どうしても情報の問題というのが出てくるのですが、それを踏まえていかないといけないので、過去のかんぽ生命の問題が終わって何か成長したというつもりは全くなくて、常にそういう原点に戻らなくてはいけないと思っています。同じように見えるのであれば、それも甘んじて受けて、そこを直していかなくてはいけないと思います。
- 【記者】
- すいません、最後の質問です。これまで不祥事が起こるたびに、研修を行ってきたと思われるのですけれども、この、なぜ不祥事がとまらないのかという部分なのですけども、今回、再発防止策の中に研修が入っているのですけども、この実効性ってあるとお思いですか。
- 【社長】
- それでもやはり研修はやらないといけないと思います、商品を販売するので、常にどこの企業も研修を行っています。その中に、不正が起こらないようなことをちゃんと取り入れていかないと、もっともっとひどくなる可能性があります。研修は必ず行っていく必要があると思いますが、その内容を要請に合った形で、きちんと行ってまいります。これは非常に関係する社員の裾野が広いので、レベルを決めてやっていかなければいけないと思っています。
- (※記者会見における発言および質疑応答をとりまとめたものです。その際、一部、正しい表現・情報に改めました。)