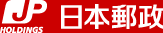- 現在位置:
- 日本郵政ホーム

-
日本郵政株式会社の社長等会見

- 2025年2月5日 水曜日 日本郵政株式会社 社長会見の内容
2025年2月5日 水曜日 日本郵政株式会社 社長会見の内容
- [会見者]
- 日本郵政株式会社 取締役兼代表執行役社長 増田 寬也
- 【社長】
- 本日は私から2件、発表させていただきます。
まず1件目です。日本郵便が提供している「郵便局アプリ」への新たな機能追加について申し上げます。お手元に資料をお配りしておりますので、そちらをご覧ください。
「郵便局アプリ」は、郵便局のサービスをいつでもどこでも便利でお得にご利用いただける日本郵便の公式無料アプリです。2023年10月にサービスの提供を開始して以来、これまでに金融相談予約機能や「かんぽマイページ」との連携機能、そして日本郵政グループ独自のポイントサービスである「ゆうゆうポイント」の来局ポイント取得機能など、様々な機能を追加してきました。このたび、お客さまにより便利に郵便局のサービスをご利用いただくために、主に郵便物流に関する機能を三つ追加いたしますので、簡単に概要を申し上げます。
まず一つ目は、「ゆうパック」の配達予告など荷物の受け取りに便利な機能の追加です。現在、メールとLINEで通知を行っております「ゆうパック」のお届けに関するお知らせを、「郵便局アプリ」のプッシュ通知によりご確認をいただけるようになります。併せて、プッシュ通知のあった「ゆうパック」について、配達予告時に事前に受け取り日時や受け取り場所を変更できるほか、不在持ち戻り通知で再配達の依頼が可能となります。受け取り場所は、コンビニエンスストアや宅配ロッカーの「はこぽす」など、お客さまのご都合に応じて、ご自宅以外の場所にも変更することができるようになります。
二つ目は、アプリ内の事前決済により「ゆうパック」を発送できる機能で、発送場所として、駅、スーパー、ドラッグストアなど、全国約5,500カ所に設置されております宅配便ロッカーの「PUDOステーション」を新たに選択できるようになります。
また、「郵便局アプリ」上で直接集荷をお申し込みいただけるよう、メニューを追加いたします。
三つ目は「e転居」のお申し込み機能の追加です。「e転居」は、インターネット上で郵便物などの転送サービスの届け出ができるサービスです。郵便局アプリ上で「e転居」を申し込みいただけるようになるとともに、より簡便にお申し込みいただけるよう、申し込みに必要な本人確認書類の読み取り機能も改善をいたします。これらの機能は、2月10日よりご利用いただけるようになります。今回の機能追加によりまして、これまで以上にお客さまの生活とニーズに寄り添うツールとして「郵便局アプリ」を活用いただき、郵便局のサービスをより身近に感じていただければと思います。
なお、新機能の追加に合わせて、キャンペーンの実施も予定をしております。各機能の詳細などにつきましては、別途、近日中にお知らせをさせていただきます。「郵便局アプリ」は、昨年の12月30日時点で400万ダウンロードを突破いたしました。ちょうどサービス提供開始から約1年2カ月で、ここまで多くのお客さまにご利用いただいておりますこと、大変ありがたく、また感謝を申し上げます。今後、当グループ各社のサービスとの連携によりまして、「郵便局アプリ」で郵便局の幅広いサービスをご利用いただけるよう、さらなる機能追加を進めてまいります。
続いて2件目です。3月3日から3月31日の期間に実施をいたします「ゆうパックでゆうゆうポイントプレゼントキャンペーン」についてです。3月は卒業や新生活に向けた準備など、生活の変化が近づく中、改めて大切な方とのつながりに思いを巡らせることが多くなる月だと考えます。その時期に、「あなたとあの人を結びちょっとしあわせにする」、これをコンセプトとした「ゆうゆうポイント」を送り、分け合えるキャンペーンを実施してまいります。
具体的には、郵便局の窓口で「ゆうパック」の包装箱をご購入いただいたお客さまに、差出人さま、受取人さまの二つの2次元コードが印刷されているカードを、先着数量限定で配布をさせていただきます。包装箱を購入された差出人の方は、受取人の方向けの2次元コードが印刷された部分を切り取って、お荷物に入れて差し出していただきます。受取人の方は、受け取ったお荷物に、同封されたカードの2次元コードをスマートフォンなどのカメラで読み取り、応募サイトから「ゆうID」でログインをいただきますと、「ゆうゆうポイント」25ポイントを受け取りいただけます。
また、差出人の方は、お手元に残していただいた差出人さま用の2次元コードを使用して応募していただきますと、同じく25ポイントお受け取りいただけるようになります。これらキャンペーンなどでためていただいたポイントは、郵便局ならではの限定商品、大切な人とつながりを深める商品との交換や抽選、ご家族へのシェアなどにご利用をいただけます。
ただポイントをためるだけではない、大切な人とお客さまを結ぶお手伝いをしてまいりました郵便局ならではのキャンペーンとなると考えておりますので、この機会にぜひ多くのお客さまにご参加をいただければと思います。
当グループでは、グループDXの推進に向けて、「ゆうID」を軸としたグループ各社とのサービス連携によりまして、「ゆうID」でご利用いただけるサービスの拡充と利便性の向上を図ります。また、お客さまお一人お一人に応じた最適なご提案をタイムリーにお届けできる環境整備を行ってまいります。併せて、今申し上げました「ゆうゆうポイント」につきましては、昨年11月の報道発表時にお伝えをいたしておりますが、この春には郵便局窓口でのお買い物や「ゆうパック」の差し出しなどでもポイントをためられるようになります。その関係については、別途発表させていただきたいと思います。
2026年度、今から言うと正式には再来年度になりますが、来年のいずれかの時期には、ためたポイントをお支払いにもご利用いただけるなど、今後もお客さまの体験価値向上に資するサービス拡充を順次行っていく予定としております。
私からは以上でございます。
- 【記者】
- 日本郵便さんとヤマト運輸での協業の件についてお伺いします。小型薄物荷物などの配送を巡って、両者の基本合意が破られたとして、日本郵便が昨年12月にヤマト運輸への損害賠償を求める訴訟を起こされました。前回の増田社長の会見では、物流や環境問題などの社会的な大義を前提によく協議したいというお話もありましたけれども、今回の提訴に至った判断についてお聞かせください。またもう1件、ヤマト運輸が先月、「ネコポス」の提供継続も発表しました。本来であれば、2月からは「クロネコゆうパケット」に切り替わるはずだったので、日本郵便側は遺憾の意も表明されています。今回のこのヤマトの発表内容による御社への影響や今後の提携についてお考えをお聞かせください。よろしくお願いいたします。
- 【社長】
- お答え申し上げます。まず、ヤマト運輸様との協業を進めていく、その大きな動機は、2024年問題の解決やCO2の排出を削減するという大きな社会的大義を両社で確認し、合意した上で進めてきたものでありまして、この点は今後に向けても協力し合うというところはますます必要になってくると思います。ヤマト運輸様もいろいろな事情があるとは思いますが、今後も一度合意した精神で、社会的大義を守るということで考えていただければ、私どもはいつでも門戸を開いていますし、今後もそういう社会的大義を守るために協議を進めていくというスタンスは全く変わりございません。
その上で、「ネコポス」の提供継続を先月、ヤマト運輸様のほうで発表されました。本来の協業の合意事項の内容によれば、今月からは全量、「クロネコゆうパケット」に移行するはずですので、基本合意の趣旨に反しますし、内容自体、私どもは全く知らされずに出されたものです。「ネコポス」を継続しながら、「クロネコゆうパケット」については私どものほうで運んでほしいという申し出もいただいていますが、本来それは相いれないものではないかと思います。しかし、お客さまの利便性を損なうことはいけませんので、しっかりと誠実にお届けするということは続けていきたいと思っております。
ヤマト運輸様の突然の発表があり、やや戸惑うところもありますが、オペレーションについては、合意の内容を守って進めていきたいと思います。それから、先行しておりました「クロネコゆうメール」は全量を予定どおりやっておりますので、私どもとしてはいつでも、先ほどの社会的な大義のことも含めて、相談をする門戸は開いておきたいと思います。
ただ、昨年の12月2日に、ヤマト運輸様より履行の義務や法的責任はそもそもないといった文書を頂戴しております。それは協業の趣旨に反しますし、合意事項に反するのではないかということで、法的責任の点については司法の場で解決するしかないかということで、訴訟に至ったということでございます。
- 【記者】
- よろしくお願いいたします。二つありまして、ちょっとほかの企業からの話で恐縮ですけれども、まずフジテレビさんのCMの関連で、各企業、CM差し止めをやめるのかやめないのか見極め中だとは思いますけれども、もともとの出版社側の訂正記事もあり、そうじゃなかったのではみたいなところもあって戻りつつある企業さんが多少いらっしゃるような向きもあるのですけれども、日本郵政グループとしては、今後どうされる見通しがあるのか、第三者委員会まで待つのかというのが1点目です。
- 【社長】
- 今、ご質問にもありましたとおり、第三者委員会が立ち上がり、伝え聞くところによると、3月下旬までにはその報告書が提出されると聞いております。第三者委員会の報告書が出た後、それを見た上で、フジテレビ様として、何らかの対応を行うことになるだろうと思います。第三者委員会が作成をした報告書と、それに対応したフジテレビ様の対応策を見たうえで、恐らく4月以降になると思いますが、テレビCMを当グループとして再開するかどうかを判断したいと思います。
- 【記者】
- ありがとうございます。もう1点が、ちょっと引っかけるようでなんですけれども、今日まさにホンダさんと日産さんが、経営統合、非常に難しいような流れになっておりまして、ヤマトさんとなんですけれども、やはり同業他社がやっていくのは民間、純粋な民間同士でも非常に難しいということが、自動車さんでさえそうであると。日本郵便とヤマトさんだと、そもそも成り立ちも違いますし、やっていくのが非常に難しいのかと改めて感じてしまうのですけれども、つい先日、決算会見で、ヤマトさんは、さっき質問があったように、「ゆうパケット」と「ネコポス」は併存していくみたいな、どっちもやっていくみたいなことをおっしゃっているのですが、やっぱりこれは裁判になっちゃっていますけれども、続けていくのは非常に、解決策を見つけるのは難しいと思われますか。
- 【社長】
- おそらく自動車業界においての2社の状況は、取り巻く環境の激変の中で様々考慮の末、先日の発表を行い、その後の交渉の中で違いが生じている部分もあろうかと思います。置かれている状況や環境が違うところはございますが、私どもと、いわゆるヤマト運輸様との関係については、2023年6月を起点として、1年と少したった段階で、180度先方の意向が変わる形になっています。私どもが伝え聞くところによると、やはり非常に経営状況が悪いため、それで背に腹は代えられないということが大きな理由ということで聞いておりますが、途中からまたその状況が変わってきているようです。
また、先日も「クロネコゆうパケット」の取り扱いについて、私どもの意向とは関係なく突然発表されたというようなことがあるため、ヤマト運輸様側の法的な責務をちゃんと確認するために訴訟を提起し、そこでご判断いただくということにさせていただいたものです。大きな社会的大義と申し上げましたが、ドライバーの確保の問題、物流の質の向上、そして環境問題については、物流に関係する各社全てが今直面している問題でありますので、そういった環境を十分理解していただければ、協力できるところはまだあると考えています。ヤマト運輸様のそういう理解が進むことを期待しつつ、いつでも協議の門戸を開いて、真摯に対応していきたいと思っています。
訴訟については、今月から全量移管という約束でございましたので、現実、もう損害が発生している状況ですが、法的責務はないとヤマト運輸様はおっしゃっておりますので、そこは訴訟で確認をさせていただきますが、協議の門戸は、常に開く形で臨んでいきたいと思います。
- 【記者】
- 今の質問に関連して、協議の門戸を開くということなのですけれども、日本郵政、日本郵便のスタンスとしては、向こうから来たら協議するということなのか、訴訟の間でも、こちらから何か働きかけする考えがあるのか、そこをちょっと教えてください。
- 【社長】
- こちらからは十分申し上げております。一昨年の6月から昨年の夏ぐらいまではヤマト運輸様も同じトーンで話しておられましたので、そのあたりに考え方を戻していただき、ヤマト運輸様からそういった考え方が当方に伝えられれば、私どもとして真摯に相談には乗っていきたいということであります。
- 【記者】
- 訴状が届いたとみられる後に、ヤマトから何かアクションはあったのかということと、あと、法務の執行役員とか、何ですかね、話し合いをされているのかとか、そこら辺はいかがですか。
- 【社長】
- 私どもが訴訟提起を発表した後、昨年12月25日に「クロネコゆうパケット」の取り扱いを年明けも引き続きお願いしますという要請が急にありました。その後、1月22日に、2月以降も「クロネコゆうパケット」を続ける一方で、「ネコポス」も併存させるといった発表をされております。このような状況に若干戸惑いつつ、本来そういう契約でしたので守ろうと思っていますが、ただ最近は、協議は対面ではなくメールのやりとりで、かなりヤマト運輸様から一方的に通知が来るような場合が多いと日本郵便から聞いております。
- 【記者】
- 同じテーマで恐縮なのですけれども、門戸は開いていきたいというお言葉についてなのですけれども、スタンスとしては理解できる一方で、今のご説明もありましたけれども、フェース・トゥ・フェースでのコミュニケーションはなかなか難しい状況になっているという中で、実際にもう一度、合意の精神に立ち返ってということが実現可能なのかどうかというのは、外から見ていると、なかなかやっぱり難しいのかなと思うのですけども、本来に戻る可能性というのは、増田さんの中でどの程度あるとお考えですか。
- 【社長】
- 俯瞰して捉えれば、物流各社は激しい競争は行っていますけれども、それだけでこれから全ての問題を乗り切れるわけでは決してないだろうと思います。各社それぞれがいろいろな状況を抱えていると思いますが、お互いの個別の事情を超えるということは、しっかり考えていかなければいけないと思います。
今回の行為を見て、私どもの担当レベルで努力してきた人間にとってみると、ヤマト運輸様に対して正直複雑な思いを持っているとは思いますが、それを乗り越えるべき状況なのかどうかは、これはまさに判断が求められます。しかし、物流業界には、大きな課題が横たわっていますので、それを考えると、今回のあつれきがあるからというだけではなかなか済まされないところが私はあると思います。
一度崩れかかると、信頼関係を再び構築するのは大変ですが、経営上の問題があるにせよ、先方からの当初の申し入れは、やはり社会的な問題に対して荷物の扱い量が非常に多い両社で解決策の方向性を示していこうということでありましたので、いろいろ社内的な採算上のことはあるかもしれませんが、もう少し歯食いしばって、守ってほしいというのが率直な思いでございます。今後の展開については、どういう形であれ、私どもとしては対応していく覚悟はございます。
- 【記者】
- つまり、人手不足だとか、そういう社会的な環境というか、大きい課題というのは今後も続かない中で、短期的には各社の事情はあるかもしれないけれども、それを乗り越えるためには、やっぱり大局的に大手同士が手を組む必要性というのはやっぱり変わらないだろうという、そういうお考えですか。
- 【社長】
- 将来的には、今回の両社のことは別にしても、もっと考えていかなければいけない分野ではないかなと思います。昨年の2月には、岸田前総理の元で、官邸でこの関係の閣僚会議が開かれて、経産大臣や国交大臣など、複数の大臣が集まり、事業者側も、私どもやヤマト運輸様といった大手3社の社長や、トラック協会様が集まりました。2024年問題などを乗り越えるために、それぞれの思惑を超えて、大きな目的を遂げるために協力していこうという趣旨を確認する会議で、私も発言しましたし、それからヤマト運輸様の社長も、以前は信書便の関係でお互いに反発し合ったところもありましたが、大きな問題があるので、乗り越えて、両社団結しましたと、岸田前総理の前でお話しました。
経営者としてもこういった状況を理解していく必要があると私は思いましたし、そのためには、もっと私どもも踏ん張らないといけないと考えました。今は決して期待されているほどの量ではありませんが「クロネコゆうメール」と一部「クロネコゆうパケット」も運んでいますが、そういう小さなことは言うべきではなく、もう少し俯瞰して捉えなければいけないと思っています。
- 【記者】
- 2点伺わせてください。1点目、昨年の10月に値上げをされ、郵便料金の値上げをされて、今年の元日の年賀郵便物が34%減というような形で数字も出ているところで、当初の値上げによる計画値と今の状況というのはどのようなイメージで認識されていらっしゃるのかというのが1点。
あともう一つ、今、自民党のほうで郵政民営化法の改正の議論が進んでいて、ゆうちょ、かんぽの株式については、当分の間保有義務を設けるだとか、あるいは将来的には、郵政と郵便の合併みたいなところを付則として盛り込むというような、そういった議論もなされていますけど、こちらについての今の増田社長のご認識を伺えればと思います。
- 【社長】
- まず、料金値上げと年賀の関係ですが、料金の値上げは昨年10月からでしたが、その月に衆議院議員選挙がありました。また、昨年9月に駆け込みでの需要があり、少しならして実際の影響を見る必要があると思っていました。そうすると、値上げの影響を見るのには、先行指標としては年賀が一番大事だと思っていたのですが、今回、元日の年賀の配達数はだいぶ減少しました。現在、正確な数字を精査しているところですが、年賀離れという、近年続いてきた世の中の動きに値上げが重なり、減少するだろうと思っていた下限に近いラインで推移しているというのが現在分かっている状況です。
それから今まで年賀状でやりとりをされていた方もだいぶ高齢になって、「年賀状じまい」をされる方も多くなってきたということも影響していますし、値上げによることで経済的な負担がかかり、続けられるけど枚数をだいぶ少なくされるという声も届いています。
今申し上げましたように、値上げによっての影響については、一応予定していた中での一番下限を少し上回るぐらいで推移していますので、それを予想の範囲と言えば予想の範囲ではあるのですが、結構厳しい数字であるということは言えるかと思います。
次に、法案については、自民党でいろいろお考えになっていて、立法府で議論されるお話かと思いますが、一言で言えば、私どもの経営にプラスになるような内容にしていただきたいと考えております。やはり上乗せ規制ですとか、いろいろな規制がかかっておりますけれども、経営の自由度が発揮できるような、そういう内容にしていただけますとありがたいということを、問われた場合には申し上げているところであります。
- 【記者】
- 今後、地方創生に向けて、郵便局、日本郵政グループとして、いろんな共創、されてこられたと思うのですけれども、それらを組み合わせる形で、郵便局を地域の複合的な拠点としていくようなお考えっていうのは何か計画がありますでしょうか。
- 【社長】
- 特に自治体中でも町村部が多いのですが、町の中心に役場があり、そこに人が多く集まる場合があります。そういったところで郵便局をうまく活用して、例えば郵便局と役場を一緒にするとか、あるいは少し離れた場所であっても、役場の仕事を郵便局で請け負うことで役場として郵便局を使いたいという場合はお受けして、郵便局も今までの決められた業務にとどまらず、地域のニーズに応じて業務の範囲を広げていきたいと思っています。こういったことを自治体や総務省の旧自治省部局などにお話していたところ、今年の4月からの予算で、法案が成立したらということになりますが、地域において買い物の手段がなく不便を感じられている方々向けの買い物支援を郵便局で行う場合や、郵便局を遠隔診療が行える場所にしていくといった取り組みなどを行った場合には、自治体に対して特別交付税が交付されることとなっており、自治体が郵便局を地域のニーズに応じて活用しやすくなるように後押しするような形で予算が組まれていることを確認しています。
郵便局は民間企業ですので、そこに所在する自治体に交付税を認めるというのは通常だとあまり前例がないのですが、その地域に郵便局しかないといった場合も多く、このような地域には予算を認めようということで、これが一つの突破口となり、ほかの機能も郵便局が果たしやすくなる措置が考えられるのではないかと思っています。今ご質問いただいた、総合的な機能を有する郵便局を実現していくための足掛かりになるのではないかと考えております。
私どもも、今回認められたものを積極的に活用し、地域でより多くの機能を果たすことができるよう、いろいろアイデアを考えておき、必要であれば、制度改正を役所のほうに積極的に提案していきたいと思います。
- 【記者】
- 今、オンライン診療の話も出たのですけれども、これからとても動きが出てきそうな気配も感じるのですけれども、日本郵便様の中に何かその専門部署、オンライン診療を広げていくみたいなものを立ち上げていかれるようなお考えっていうのはありますでしょうか。
- 【社長】
- 今は、オンライン診療に特化するよりも、現在の地方創生の取り組みの中で、その関係も十分対応できると思っています。現状は、基本的に病院か診療所を中心に、特に地方では診療所でのオンライン診療が進められていますが、今回の予算案を見たところ利便性を考えて郵便局や駅にオンライン診療の拠点を認めるような内容になっておりました。初めはそれほど拠点が多くないと思いますので、今の地方創生を行っている部署で十分こなせると思っていますが、将来的に拠点が増えた場合の対応については今後検討していきたいと思います。
- 【記者】
- あと、それに関連して、今後の考え方として、大企業だけじゃなく、中小規模の地元企業や、あと例えばデジタル系やネット関連で拠点を持たない企業ってこれからどんどんまた増えてくると思うのですけど、そういう企業と提携するような計画だとかありますでしょうか。
- 【社長】
- 企業規模でいうと、スタートアップや小規模な企業からの提携の提案も随分多く案件が持ち込まれています。うまく実るものもあれば、そうでないものもあるようです。私どもとしては、特に地方の場合にはほとんどが中小企業ですので、そういったところともいろいろ話し合いを進めていきたいと考えております。
また、郵便局のスペースについて、集配機能を地方で統合することで郵便局に空いているスペースが多くあります。このスペースを有効に利活用するということで、テレワークオフィスのようなものも考えられますので、もっと地域のニーズを見ながら進めていきたいと思います。例えばこの近辺でも、横浜の青葉台郵便局では1階は通常の窓口業務が行われていますが、2階と3階は、東急様と提携して、個人がレンタルできるお洒落なテレワークオフィスのような形で使えるようになっております。このような取り組みは、地方部のみならず、都会の郊外部などでも、今後も考えられるだろうと思います。
- 【記者】
- あと、外国人の方が郵便局を利用されることが増えていると思うのですけど、その窓口対応で新しい動きのようなものはありますでしょうか。
- 【社長】
- 言語の問題で手続きに、お客さま一人一人に時間を要することがあるため、お客さまご自身のスマートフォンで利用可能な「ゆうちょ手続きアプリ」の利用勧奨やゆうちょ銀行直営店に設置しているMadotabといったお客さま対応用のツールを利用していただいて、翻訳できる言語を増やして、ご自分で簡単に口座開設などができるようにしていこうと考えております。
また、多くの方が来る郵便局の窓口では、近場に外国人を雇用している企業があったり、語学学校や大学があったりするような場合、10月や4月といった決まった時期に、特に東南アジアの方が多いように聞いておりますが、多くの外国人の方が窓口にいらっしゃると聞いております。これらの時期には、企業や学校に対して日本語が分かる付き添いの方も来局いただくように、また、少し分散して手続きをしに来ていただくようにお願いしています。手続き自体もできるだけ簡素化にするように努めています。当グループでは利便性を高めるように努めておりますし、さらに今後も改善していきたいと思います。
東南アジアの言語は結構複雑で、文字だけではどこの言葉か判別できないということも多いようなので、いずれはAIを活用できるようになればいいと思っていますが、当面はアプリなどのツールの利便性を高めて対応し、必要に応じて、企業や学校からもご協力いただいて、分散対応するといったようなことで乗り越えていきたいと思います。
〔注〕以下の質疑応答模様について、後日事実関係を確認した結果を本会見内容の最後に注記しております。
- 【記者】
- 別件で日本郵便が、「ゆうパック」の委託先業者から徴収している違約金についてお伺いいたします。昨年6月に、一部の郵便局が委託先の配達業者から不当に違約金を徴収していたということで、公正取引委員会が下請法違反を認定して、是正を求める行政指導を行いました。この事実についてなのですけれども、日本郵便の取締役でもある増田社長が、いつ、どのような経緯でこの事実を把握して、その後、日本郵便、日本郵政内でいつどのように情報共有をされたのか、教えていただけますでしょうか。
- 【社長】
- 私がこの違約金の関係で下請法違反だということを把握したのは昨年12月の下旬です。それこそ御社から質問があったと思いますが、それで把握をしたのが私の最初です。価格転嫁の関係は公正取引委員会から話があり、ご承知のとおり中小企業庁で公表されたこともありますし、価格をちゃんと転嫁しているかどうかというのは気にしておりましたが、違約金については制度自体、どうなっているか分かりませんでした。その後、この問題の対応を、その時点で日本郵政の中でも情報共有されておりますので、それで対応しております。
聞いたところによりますと、昨年6月に一応、日本郵政にもメールでいろいろな案件の一つとして連絡があったようですけれども、おそらく十分な情報共有がされていなかったと思います。
- 【記者】
- 増田社長がこの情報を把握したのは、朝日新聞は昨年の12月18日に日本郵政とですね、日本郵便に、この違約金制度の下請法違反で行政指導に関して質問状をお送りさせていただきました。この時点で把握されたということでしょうか。
- 【社長】
- 正確な日付については分かりませんが、おそらくその時点だと思います。
- 【記者】
- それまでですね、この下請法違反を認定されて是正を求める行政指導を受けたということが情報として共有されていなかったということですけれども。
- 【社長】
- 日本郵政には共有されていないです。日本郵便の中で対応していたと思います。
- 【記者】
- 日本郵便の取締役として把握はされていたのでしょうか。
- 【社長】
- していないです。担当ベースで対応をしていたのだと思います。
- 【記者】
- この件は下請法の違反まで認定をされている事案ですけれども、それが取締役含めてですね、共有されていなかったということについて何か受け止め、お伺いできますか。
- 【社長】
- いろいろ行政当局から指導などを受けているときに、特に重要事件や重要事案はやはり共有すべきだと思いますので、その点も十分じゃなかったと思います。
- 【記者】
- 具体的に昨年12月の下旬までは、どの担当者のところまでしか情報共有ができていなかったのでしょうか。
- 【社長】
- その点については、日本郵便に聞いていただければ分かると思います。
- 【記者】
- 昨年6月下旬にこの行政指導がありましたけれども、今回、ここまで下請法違反の認定内容まで踏まえて、当時、行政指導を受けて情報共有はどこまで、本来、どの段階でするべきだったと思いますか。
- 【社長】
- 一般論でいうと悪質なものについては、やはりちゃんと情報共有されるべきだと思います。それは当然トップまで情報共有されるべきです。それから担当ベースで済むような、いわゆる軽微なものは、そこでちゃんと措置がとられていればいいと思います。今回は日本郵便で本来全部処理していなければいけない事案だと思いますので、そこが十分にスピード感を持って処理されてなかった事案かと思います。そういう点での対応は決して良いものではなかったと思います。
- 【記者】
- 改めてですが下請法違反と是正を求める行政指導を受けたということについては、どのように受け止めていらっしゃいますか。
- 【社長】
- 日本郵便のとある局の問題で、公正取引委員会からの是正指導があったということですが、協力会社様とは対等のパートナーとして、これからも関係を築いていかなければいけません。本来そういうことがあってはならないと思いますし、それから価格転嫁の問題が公表されたこともあり一番に対応していたのですが、違約金の問題も対応が十分でありませんでしたので、早く是正をしていく必要があるということが、教訓として出てきた問題だと思います。
- 【記者】
- 実際に行政指導を受けて、違約金制度の変更の通知を、全国の郵便局に出したのが昨年12月19日でした。これも対応としてスピードは遅かったと捉えていらっしゃいますか。
- 【社長】
- 昨年6月に指導を受けているようで、その中での状況把握と、それから公正取引委員会とは夏以降も随分とコミュニケーションをとっており、その上で出したということですので、できるだけ早く出したものと受け止めております。
- 【記者】
- そうすると、この昨年12月19日の違約金の制度変更については、要は社外取締役含めた、取締役会に諮って意思決定をしたわけではないということですか。
- 【社長】
- 諮っておりません。
- 【記者】
- この件を取締役会に諮らなかったということについて、どのように考えていらっしゃいますか。
- 【社長】
- 諮るかどうかは違約金を担当する部署の判断になりますが、下請法違反で指導があり、今後こういった対応をしますという方針を報告しておけば、事細かなルールまでは取締役会に諮る必要はないと思います。日本郵便もさまざまな指導を受けていると思いますので、そこの軽重に関わってくると思いますが、スピード感としても日本郵便の取締役会の開催日程に間に合わなかったのだと思います。
- 【記者】
- 一応、会社法ではですね、重要な業務執行の決定については取締役会の専決事項と規定されていますけれども。
- 【社長】
- 物事の決議までとる案件ではなくて、執行側の姿勢に関わる話ですので、そこは日本郵便の判断になると思います。
- 【記者】
- なんていうか、その今回の違約金制度で不当な徴収があったということについて下請法違反の認定と行政指導を受けて、それを受けての制度変更になるわけですけれども。その制度変更も重要な業務執行の決定には当たらないという認識でいらっしゃるのでしょうか。
- 【社長】
- 内容によるとは思いますが、昨年6月に指導を受けたときに、公正取引委員会とコミュニケーションをとっていたようですので、早い段階で取締役会にこの方向で対応しますと報告しておけば、それで済んだ案件だろうと思います。今年1月の取締役会で報告がありましたけれども、早い段階でそういったことが行われていればよかったのではないかと思います。
- 【記者】
- もう1点関連してなのですけれども、この行政指導を受けたのが昨年6月下旬で、昨年の8月に、日本郵便として全国の郵便局を対象に、下請法違反認定されたものと同様の事案があるのかどうかということを調査して、その結果、同様の事案は認められなかったと、我々の取材に対して日本郵便は回答しています。それをもって同様の事案は認められていないという、結論づけているわけですけれども、全国の郵便局を対象に行った調査が、同様の事案があるのかどうかを確認する上で正当な調査だったと考えられていますでしょうか。
- 【社長】
- 調査が不十分だったという趣旨でのご質問でしょうか。
調査自体は全国で集配を扱っている約1,000局全部を対象に調査したと聞いています。対象局の窓口の担当に確認すれば状況把握できると判断して調査したのだと思います。虚偽の申告があれば論外ですけれども、お話のあったような報告結果が出たと聞いております。
- 【記者】
- 一方で不当な違約金の徴収に関する調査手法としてですけれども、実際に徴収する側の郵便局を対象にしかしていない調査であって、本来、不当な徴収をされたかどうかというのは徴収された側のですね、委託先の配達業者からの聞き取りも必須だと思うのですけれども。
- 【社長】
- もちろん協力会社様も併せて両者に調査ができればよりよかったと思います。
- 【記者】
- そうすると調査としては不十分だったというふうにお考えですか。
- 【社長】
- 日本郵便で現場のことを一番よく知っている担当者が、窓口の社員が虚偽の申告をしないだろうという信頼感で、素早く状況を把握するために判断したのだと思いますので、それはそれでいいと思います。
今大事なのは協力会社様とたばこの臭いなどが荷物についてしまっているといった苦情がお客さまから多く来てしまうことに対して、お互いにそれを防止するためにどうすればいいのか協議をすることだと思います。これについては、現在、郵便局を通さず本社から直接全ての協力会社様に意見を聞いておりますし、こういった協議は常にやっておく必要があると思います。
- 【記者】
- 我々の取材では、今回、公正取引委員会の下請法違反を認定した当該の事案とは別に、その違反の認定に照らして、同様の不当な徴収を受けたと訴えていらっしゃる、あるいはその事実関係も踏まえて、取材でそういう事案が別のところであったということも確認、把握をしています。
一方で、社長もおっしゃったように、本来であれば、委託先業者も調査の対象としたほうがよかったと今おっしゃいましたけれども、改めて、その同様の事案がなかったのかどうか、再調査をするような考えというのは、現時点でありますか。
- 【社長】
- 今、協力会社様に郵便局だと言いづらい内容を含めて答えてくださいということで本社から直接お聞きをしております。おそらくご不満が出てくるのだと思っておりますので、これが今ご質問された調査になるのだろうと思います。
- 【記者】
- それは、昨年の8月以降に改めて調査をしたということですか。
- 【社長】
- 今やっている調査です。
- 【記者】
- それは委託先業者を対象にやっている。
- 【社長】
- 協力企業様を対象に実施しています。コミュニケーション期間をつくり、1月20日から実施している最中です。この結果は本社に直接来ますので、ご不満があればその中に記載があるのではないかと思います。
- 【記者】
- 分かりました。今回で違約金制度の変更については、昨年の12月19日に1回目の変更通知を行って、その約1カ月後の今年の1月20日に、改めて、再び変更したという通知を1月20日に行いました。1カ月の期間で、この下請法違反を受けての制度変更が2回行われたというのは、通常考えられないような異例なことなのかなと思うのですけれども、この1回目の制度変更にどのような問題があって、2回目の変更をわずか1カ月のうちにしたのでしょうか。
- 【社長】
- 4月から実施となるため、内容に不十分な部分があれば早く通知し、直したほうがいいと判断しました。誤配や荷物のたばこの臭い移りについて、違約金のみで解決するというのは、今、求められていることとは少し違うと思っています。ご本人に研修を受けていただくなり、協力企業様にも協力していただいて、お互いによく話をして、誤配や臭い移りがないようにしていきましょうという姿勢が今は必要だと思っておりますが、その部分の考え方が、昨年12月の通知書には入っていなかったので、日本郵便の姿勢や考え方が、協力会社様のほうで酌み取れないものは早く変えたほうがいいので、1月20日にその考え方を反映させた通知書を出したと理解しています。
- 【記者】
- 2回目の制度変更は、取締役会で意思決定をしているのでしょうか。2回目の、1月20日。
- 【社長】
- 郵便の取締役会で決議はしておりませんが、報告はしております。
- 【記者】
- 実際に1回目の変更通知を受けて、それで全国の郵便局は委託先業者にこういう制度変更すると説明をもうしている中で、今回2回目の制度変更が行われたということで、現場では混乱していると取材で聞いているのですけれども、このあたり、1カ月で2回の変更をしたことについて、何か問題はなかったと思いますか。
- 【社長】
- それでも直したほうがいいと思います。郵便局に考え方を示して、4月に向けて、今ちょうど多くの協力企業様の方々と相談しているところですので。場合によっては、もう相談を始めていたところはおわびをしてでも、より間違いのない方向で実施したほうがいいのではないかと思います。
- 【記者】
- 2回目の制度変更で、1回目の変更に関して、もっとこう変更したほうがいいという声は、取締役会の中で上がっていたということですか。
- 【社長】
- 取締役会ではなく、会社の中で、もう一度よく考えてということです。
- 【記者】
- すいません、長くなって。いずれのですね、1回目と2回目の制度変更でも、これまで不当に徴収されたというようなですね、違約金については、この通知の文書を見ると、高額だと委託業者から返金要請があったとしても、合意があったのであれば、返金に応じないという旨の方針が示されています。ここで言う合意の定義、あるいは返金についての考え方というのは、どのような形で運用されるようになっているのか、お伺いできますでしょうか。
- 【社長】
- 法的に合意の定義と言われても難しいところです。
- 【記者】
- 例えば、その違約金の契約自体は交わしているということをもって合意と捉えていらっしゃるのか、あるいは、もっとその本質的なところで。
- 【社長】
- まず一つは、下請法違反と言われた個別の案件がありました。その件については違反ですので、既に返金しております。その他の個別の案件について把握しておりませんが、違反した郵便局と同じレベルのもので、法的に評価して、違反だと考えられるものであれば、返金する必要があるのだと思います。そこまで至らないというものであれば、必要ないかもしれません。あとはもう個別で判断していかないと難しいと思います。
- 【記者】
- 改めてになるのですけど、この、今回の制度変更を2回行ったということについてなんですけれども、その情報共有は、本来、行政指導の直後から早い段階で共有されるべきだったと、行われるべきだったということだったのですけども、制度変更に関しても、そういう広く情報共有をした上で、意思決定も広く関わるような形で変更したのでしょうか。
- 【社長】
- 公正取引委員会から調査を受けている中で分かってきたこともありましたので、6月に文書をいただく前から、違反になる事例について現場の社員に対して研修をしていたようです。今回の件に関してもどこが抵触しているかは、担当レベルでは早い段階で分かると思いますので、それを含めて、切り替える必要がある早いうちにしっかりとまとめて、それで現場に周知するということが必要だったのだと思います。
- 【記者】
- 今回、一連の、この違法認定と行政指導について、これまで株主だったり、あるいは取引先のステークホルダーに対して、何か説明というのはされてきたのでしょうか。
- 【社長】
- 日本郵便は日本郵政の100%子会社ですから、日本郵政には説明しました。協力会社様にも特に1月20日からのコミュニケーション期間については情報をお出ししていると思います。ステークホルダーという意味では、そこだと思います。
- 【記者】
- 改めてですけど、1月1日からですね、制度変更して、改めて、まだ違約金制度自体は存続していくということですけれども、この制度自体についての受け止め、考えというのをお聞かせいただけますか。
- 【社長】
- 私が日本郵便に言っているのは、いずれにしても、目的は荷物をいい品質でお届けすることです。そのために必要な措置がどういうことなのかということです。問題になっているのは、誤配や臭い移りがある程度繰り返し起こっているということなので、どうしても品質を保てない場合には、契約を解除することになるのだと思います。ただ、協力企業様と話をすれば、改まるところが多いと思いますし、そういった問題をなくすために、ドライバーの方ともよくお話をして、こういった点について気をつけようと調整するのが今回の趣旨だと思いますので、いきなり違約金を取るのではなく、何回か注意をして、改善が見られなければ違約金をいただくと今回はさせていただきましたが、改善に結びつけるために、どういったことが、一番効果が出るのか、お客さまに不快な思いをさせずに済むのかを見ていく必要があると思います。1月20日の通知で従来とは取り扱いが変わりましたが、これで苦情が少なくなるのであればいいと思いますし、これでも改まらないということであれば、また別の視点で協力業者様とよく相談して、考えていかなければいけないと思います。
- 【記者】
- あと最後に、この一連の件を受けてですね、情報共有の遅れのお話もありました。この一連の件を踏まえたときに、日本郵便、日本郵政としてですね、ガバナンスに何か問題があったとしたら、どのようなことだと思いますか。
- 【社長】
- 大きな問題については、やはり日本郵政に共有されるべきだろうと思いますので、その点は検討して、正すべきは正さなければいけないと思います。あまり外部の方に言う話ではありませんが、指導を受けている場面というのは多々ありまして、指導にも強弱があります。お客さまにご迷惑をおかけするようなことだけは避けたいので、誤配やたばこの臭い移り、遅配などをどれだけ減らすかということで考えなくてはいけません。今回はお客さまに荷物をお届けするという業務において、協力会社様にお願いしているのですが、両社のガバナンスがどうあれば配達の品質がちゃんと担保されるのかを最優先で考えていきたいと思います。
- 【記者】
- 分かりました。すいません、情報共有が遅れた原因についてはどのように考えていますか。
- 【社長】
- それまだ分かりません。いずれにしても、直接の報告は聞いていませんので日本郵便サイドの話だと思います。
- 【記者】
- ありがとうございます。
〔注〕日本郵便が公正取引委員会から行政指導を受けた件につきましては、日本郵便の取締役に対しては、2024年6月の日本郵便取締役会における「公正取引委員会の調査結果報告」において、個別事案として報告を行っております。
しかし、昨年6月時点では、価格協議については経緯を含め詳細に報告しておりましたが、違約金については行政指導の対象となった事案についての報告にとどまっており、違約金制度やその運用実態に関する情報共有は行われていませんでした。その後、昨年8月に実施した全国調査の結果、違約金の対象事案や金額の定めなどについて郵便局ごとの運用にバラつきが生じているなどの課題が認められたことから、日本郵便において違約金制度の見直しを検討の上、昨年12月に日本郵便の経営陣に報告、同月下旬に日本郵政株式会社に対し報告を行ったものです。
- (※記者会見における発言および質疑応答をとりまとめたものです。その際、一部、正しい表現・情報に改めました。)