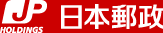- 現在位置:
- 日本郵政ホーム

-
日本郵政株式会社の社長等会見

- 2025年10月8日 水曜日 日本郵政株式会社 社長会見の内容
2025年10月8日 水曜日 日本郵政株式会社 社長会見の内容
- [会見者]
- 日本郵政株式会社 取締役兼代表執行役社長 根岸一行
- 【社長】
- 日本郵政の根岸です。本日もご多用の中お時間を頂戴しまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はじめに、私から3点、口頭で恐縮ですけれども、申し上げます。
まず、点呼業務不備事案について申し上げます。今月1日に日本郵便社長の小池からも発表させていただきましたが、本日から111の郵便局において、軽四輪車に対する行政処分が執行されております。日本郵便では、当初、特別監査が開始となった時点から準備を進めてまいりましたので、現時点で対象郵便局のオペレーションに問題が発生しているとの報告は受けておりません。今後も、お客さまに安定的にサービスをご利用、ご提供できるものと考えているところです。
それから、今月2日に、今般の法令違反に対するおわびと、郵便物および荷物のサービスの維持について、新聞広告を展開させていただいたところです。引き続き、点呼適正化に向けて全力で取り組んでまいります。
2点目、郵便物不配の非公表事案についてです。先月9月26日に、これまで非公表としていた事案について、今後公表することが適当であるとして総務省から行政指導を受けたところです。大変重く受け止めておりますが、やはり過去の非公表の事案も含めて公表すべきだと考えております。現在、日本郵便におきまして、その公表に向けて準備を進めているところです。
こちらの点もあわせまして、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいりたいと考えているところです。
3点目です。一昨日公表させていただきました、日本郵便によるロジスティードホールディングス株式会社株式の取得および資本業務提携について、若干述べさせていただきます。
当グループでは、現在の中期経営計画でも、郵便・物流事業については、資源を積極的に投入してさらなる成長の加速を図るとしてきたところです。先般、トナミのMBOも行いましたが、当グループとして物流領域については、BtoB強化に取り組んでまいりたいと考えているところであり、今回の案件も同様に、物流の川上領域に進出することで、国際から国内の物流、そしてラストワンマイルまでをトータルで手がける総合物流企業を目指していきたいと考えているものです。総合物流企業を目指した、非常に重要な施策として認識しております。
日本郵便の出資ですが、持株会社である当社といたしましても、投資対効果、それから出資の目的が最大限発揮されるように、日本郵便とよく連携をしながら、状況についてモニタリングしてまいります。物流事業の強化については、M&Aも含め、さらにさまざまなことを取り組んでまいりたいと考えております。
私からは以上です。本日もよろしくお願い申し上げます。
- 【記者】
- 冒頭のご発言にもありました、いわゆる不適切点呼のことについてお伺いさせていただきます。トラック約2,500台の貨物運送事業許可の取り消しに続いて、新たに軽貨物188台の一時停止、使用停止の処分、行政処分が出ました。この処分に対する受け止めとともに、処分を受ける、この軽貨物についての処分を受ける郵便局は2,000局規模になるというふうにもみられています。今後、配送事業や経営に関してどれくらいの影響になりそうなのかというところを教えていただけますか。
- 【社長】
- まず、点呼業務不備事案に関しましては、郵便、ゆうパックなどをご利用いただいているお客さま、関係者の皆さまに多大なるご不便、ご不安、ご心配をおかけしているところです。改めておわびを申し上げます。
この点呼業務の不備に関しましては、極めて重大な法令違反です。ましてや、私ども運送事業者としてその存立に関わる重大な事案だと受け止めているところです。これは、かねてから申し上げてきたとおり、認識は全く変わっておりません。再発防止に、まずは全力で取り組んでいるという状況です。
それから、その影響などですが、先ほどご指摘いただきましたように、まず、188台、111局の処分を受けたところですけれども、2,000局規模に広がるというような状況でして、まだ1割にも満たない状況です。したがって、そのスケジュールや順番、時期によっても、いろいろと対応が変わってまいります。どのくらいの金額がかかるのか、という点については、もう少し数が増えてくると、全体像でこのぐらいだということを推定でもお話しできるかと思いますが、今申し上げましたように、まだ数は少ないですし、そのスケジュールについては国土交通省がお考えのところであり、どういった形でというのは、私どもは把握をしておりませんので、それを踏まえた上で、適切なタイミングでご報告、お伝えできればと考えているところです。
- 【記者】
- 自民党の新総裁に高市元総務大臣がなられたことに対するご見解をお願いします。
- 【社長】
- 高市先生は総務大臣もご経験をされている方ですので、郵政事業についてもご見識のある方だと思います。それに限らず、信念を持った政治家の方ですので、いろいろな形でわが国を導いていただけるのではないかなと思っておりますし、まだよく具体的には存じ上げませんけれども、郵政事業に係る何かしらの方針がございましたら、そのご指導を仰ぎながら適切に取り組んでまいりたいと考えております。
- 【記者】
- 地公体を主に、自治体など、あと農業や漁業などの事務受託も含めて、いわゆる事務や雑務の丸ごとの受託ビジネスを、郵便局が大がかりにこれから取り組んでいくような計画というのはありますでしょうか。
- 【社長】
- もともと自治体からの事務については、特に支所などが廃止されるようなところについては、おっしゃるように、できる範囲というのはもちろんありますが、丸ごと受託をさせていただきたいということは申し上げてきています。事実、一部の市町村では、そうしたかなり多くの、広範な事務の受託をさせていただいております。こういった点については、私どもからも自治体に働きかけをして、できれば受託を増やしていきたいと思っております。
それ以外の部分、農業などについてもご支援させていただきたいところですけれども、こういったところについては、郵便局がどの程度できるかというところもあります。個別の状況をよくご相談させていただきながら、郵便局は地域の中における数少ないネットワークになっていますので、お役に立てることについては、各地域のニーズを踏まえながら取り組みたいと思っております。したがって、自治体の業務については丸ごとですけど、それ以外のことについては、どうしても個々の部分をよくご相談しながら、という形にならざるを得ないと考えておりますし、それが適当ではないかと思っております。
- 【記者】
- あと、前国会で既に提出をされている、一つの施設や複数の医療機関のオンライン診療を提供できることになる医療法の改正や、あと郵便局の公的サービスを正式な事業とするための郵政関連法の改正案の臨時国会での成立に向けた動きに対するご期待感とか、そういうものがもしあればお願いします。
- 【社長】
- 郵政の改革法案については、従来から申し上げておりますとおり、スタンスは変わっておりません。国会議員の皆さまで十分議論を進めている話ですので、私どもとしては、決められたものに対して郵政事業としてしっかりと運営していくということです。国会に提出をされたのは昨年、前回の国会のときですので、その状況については、私どもはとやかく言うよりは、議員の皆さまの議論にもお任せをしたいと考えております。
- 【記者】
- 日本郵便様が予定されている宅食サービスですけれども、例えば地方の郵便局のスペースの一部をお昼に開放して、高齢者の方とかを集めて、そこに食事を届けて、健康のコミュニティーにするなど、何かそういう局の活用の仕方などの計画はありますでしょうか。
- 【社長】
- 今ご質問いただいたようなことを、具体的にどの局でということは、私は承知しておりません。ご指摘いただいたようなアイデアは、食品を扱うときに、法律上よく確認する必要があろうかと思いますけれども、郵便局の空きスペースを地域の方々にご利用いただくというのは、今お話があったようなことも含めて、いろいろと展開していきたいと思っております。
事実、幾つかの局で、食品を置いてあるわけではないですが、お茶を飲みながらご歓談いただくようなスペースを設けている局も現実にございますので、そういった取り組みの一環、あるいは発展形として十分考えられる話だと思っております。
- 【記者】
- 仮定やいろいろと不確定要素を含むような前提の上での質問となってしまうのですけれども、ロジスティードへの出資についてお伺いしたいです。ロジスティードへの出資、足元ですね、先ほど質問もあったような郵政民営化法の改正で郵便局の維持であったり、財政支援が今検討されている状況で、垂直統合に近いような動きを見せること、特に郵便局のネットワークを強みとして、そこにこぎ着けたっていうところについて、一民間企業、上場企業としての投資としては極めて効果的なものだと思うのですけれども、一方で、業界内ではどうしてもアンフェア感というものはあるかなと思います。その辺りについて、公的側面、公的役割というのを負っている部分もあると思うのですが、社長の中でのロジックの整理といいますか、お伺いできればと思います。
- 【社長】
- 確かに政府の出資を当社は受け、株式の3分の1超をお持ちいただいております。今回、いろいろな法律改正が検討されているところですけれども、一方で私ども、ゆうちょ銀行、かんぽ生命も含めて上場しているわけです。上場している以上、株主に対する責任、収益、利益を上げて還元するということも、これも一つ責務で負っているわけですので、そうした政府の保有があるからといって、事業を限定的にというか発展を考えないというのは、これもまた片方の責務に違反をすることだろうと思っております。
恐らくほかの民営化された企業でまだ政府の出資が残っているところでも、やはり積極的な事業展開をし、株主の方、あるいはご利用者の方に、利用者利便を図るような形で取り組みをしておりますので、それは私どもも一緒だろうと思います。
ただ、もちろんイコールフッティングの観点で、いろいろな指摘があり、行政それから国会の中で、当社がゆうちょ銀行及びかんぽ生命の株式を3分の1超保有したまま新規業務を行うことなどの議論が行われたことは承知していますが、私どもとしましては、事業を広げることによって、株主あるいはご利用者に還元したいということです。しかし、そうは言ってもそういった議論は、行政、国会の中で議論されることになりますので、その範囲の中で最大限できることを尽くしていきたいというのが私どもの立場です。
- 【記者】
- 冒頭のところで、点呼の関係でちょっと触れていただいた、一応確認なのですが、最初の質疑のところで、今300局で1割ぐらいにも、1割ぐらい処分についてですね、1割か1割に満たないというのがありましたけども、改めてこの仮に2,000局ということになった場合の配送、配達への影響というのは、社長、どのように考えていらっしゃるかちょっと改めて教えてください。
- 【社長】
- これから一番忙しい12月を迎えますので、もともと業務が逼迫しているところではございますけれども、いろいろと前提条件を置きながら、個別局ごとに、どういったことができるだろうかと、さまざまにシミュレーションしているところです。
その中で、例えば委託先様、これは本当にありがたいことですけれども、今、既に委託をしているところでも、さらに協力をしてくれる、というようなこともあります。それから、処分を受けていない軽四輪車などを利用して、このぐらいはできるだろうということを個別に確認しておりますけれども、そうした中では、何とかお客さまにご迷惑をおかけすることなく、年末の忙しいところを乗り切れるだろうと考えているところです。
これから処分が出てきた都度、それに対して調整をしながら進めていかなければいけませんが、今想定しているところでは、お客さまにご迷惑をおかけすることなく乗り切れるだろうと考えております。
- 【記者】
- 私からは冒頭の不配事案の公表、非公表のところで幾つかございます。まず過去分も含めて公表すべきと判断されたというお話でございましたけれども、いつ時点のものから公表されるのでしょうか。またその公表というのはいつ頃、まとめてされるものなのでしょうか。あと、そうした非公表になった、非公表としていたその事案というのが、これまで計何件あったのか、その公表を決められたそのものからというカウントになると思いますけれども、何件あったのかまず教えてください。
- 【社長】
- いつ頃のものから公表するのかというところについては、今準備をしているところですけれども、恐らく2カ月も3カ月もかかるほどではなくて、もう少し早いタイミングで公表できるのではないかと思っております。といいますのは、これはいつまでさかのぼるかによりますけども、どうしても文書の保存期限だとかそういったことも考え合わせたときに、かなり古いものまで公表し得るかというと、正確に公表できる情報がございませんので、このところをよく見ているところです。
ただ、2021年から2024年までの間で30件ほどあることは確認しておりますので、この辺りを中心に、あとはもう少しさかのぼれるかどうか、あるいは今申し上げたような2021年以降のところについても精査した上でということであり、この辺りを今詰めさせていただいているところです。いずれにしましても、その4年間で申し上げますと、30件ほどになると聞いております。
- 【記者】
- その上でなんですけれども、今般、総務省からの行政指導があったわけなのですけれども、これまでの日本郵便としての公表、非公表の判断の対応に誤りがあったのか、何か問題があったのかどうかの認識と、問題があったというふうな判断なのであれば何が問題だったのか、この辺り持株としての認識を伺いたいです。以上です。
- 【社長】
- 総務省からもいろいろとご指摘を受けましたけれども、当初は、いわゆる部内犯罪とはなってない問題であっても、必要により報道発表するものとしていました。その「必要により」というところについて、かなり限定的に考えてきたのではないかと思います。それが今回の状況に陥った原因ではないかと思っております。
ただ、やはりご利用者の立場を考えると、個別対応すれば済むとしていたものや、DMなどかなり多数の方に送るもの、また、直接利用されていないお客さまに対しても、こうした問題があって、その是正に取り組んでいる、という旨を含めてお伝えする観点が、利用者保護、あるいは信頼をしっかりと維持するために必要なことだったのではないかと思っております。そうした観点からの行政指導だったと思います。犯罪ではないとの認識から、「必要により」ということを限定的に考えるという点で、問題を捉える意識が弱かった点は否めないと思っております。
したがいまして、今回公表することとしました。以後は、これまで非公表としてきたところも公表になるということで、その基準を見直して運用していくということになります。
- 【記者】
- 本日はありがとうございます。ロジスティードの件について幾つかお伺いさせていただけたらと思います。今回出資が約20%というところで、この比率になったというところはどうしてこの比率になったのかというところをまず教えてください。
- 【社長】
- 株式を保有されているKKR様やロジスティード様といろいろと議論を行いました。私どもとしましても、提携として、シナジー効果を得るためにしっかり手を取り合っていくという意味で、一定程度の出資を行うという総合的な判断をした結果、としか正直言いようがないところです。
- 【記者】
- ありがとうございます。それで何か将来的にこのロジスティードを、傘下に収めたいとかそういうお気持ちがあるのかというところで、何か布石になるのかとか、あとそのロジスティードが2027年に上場するという話もありますけど、そのときどういう対応するのかとか、その辺りについて将来的なことを教えていただければと思います。
- 【社長】
- 上場のタイミングだとかそういった部分については、お持ちになっているKKR様がご判断される部分であろうかと思いますので、私どもとしてどうこうという立場ではありません。今回の出資比率は適切な取得割合だと思っていますので、まずしっかりとその成果を見る。その成果を何年かたった時点、その時点で必要な対応をとるということであります。したがって、今は成果をしっかりと上げることがまず大事であって、将来、50%にするのか、あるいは売却するのか、そのままなのか、ということについては、特段何か決まったものがあって、予断を持って進めているものではございませんので、その都度、方針などに変更がありましたら、ご報告、ご説明させていただければと考えています。
- 【記者】
- ありがとうございます。まだ、現時点では日本郵政グループの中にロジスティードが欲しいとかそういうところまではまだ言えないというところで。
- 【社長】
- はい、まずは今回の提携のシナジーを出すというところまでです。
- 【記者】
- ありがとうございます。すいません、長々と申しわけないです、もう1個だけお伺いしたいのですけども、その資本業務提携という形でどれだけシナジーが発揮できるのかというところで、ほかの宅配の大手も、今3PLを強化して、宅配のシナジーを出していこうということは、いろいろ頑張ってやられていると思うのですけども、まだそこまで大きい成果というのが上がっていない中で、この資本業務提携という形でのこのシナジー創出はどこまで現実的だと思われているか教えてください。
- 【社長】
- おっしゃるように、資本提携が過半でなければ、ただ単に提携してやっていけばそれなりにシナジーはあるのではないかということはありますが、今回、資本提携に加えまして、取締役1名を出させていただくことも考えております。
そういう意味で、より強固にシナジーを発揮するためにお互い真剣にやっていきましょうということの表れだと思っております。仮に資本提携がない中で、あるいは取締役の派遣もない中ですと、今はよくても、どこかのタイミングで少し意識がずれていくということがあり得ないとは限りません。将来に向かってしっかりやっていくためにも一定の出資、一定の取締役の派遣を行う。そういった中で、人材の交流などさまざまな形で接点を持ってやっていきましょうと具体的に話ができていますので、そういった意味でも、出資をするということに対しては大きな意味があったのだと考えています。
- 【記者】
- 今もいろいろ不祥事の話、点呼とか、行政の、郵便物の公表の不十分という問題についてお話しいただきました。以前から、風通しのよい組織風土の改革ということを取り組んでおられると思うのですけれども、そのかんぽの問題に始まってクロスセル、点呼、今の行政指導の話もあって、根本的なところって、日本郵便が抱えるこの組織風土というものが根本にあると私は思っているのですけれども、今回の公表されなかった問題とかも、現場でやっぱりちょっと何というか、自分で言えない風土であるとか、かんぽのときは、世間的には、これはパワハラだというような文言とかをはいている人が、全然それはパワハラだと思っていなかったという問題もあったと思うのですよ。私もちょっとそういうのは聞いて、感じていることもありまして、だから、そういった人というか、人と、あと現場の人と上の人のコミュニケーションのこととか、そういうものも、特に指導する人の、何というか、価値観ですよね。そういったものも含めて、組織風土の改革というのを行っていくのがいいと思うのですけれども、今、進捗具合というのは、どんな、具体的なお取り組みとか進捗とか目標とか、そういったものがあったらお伺いできますでしょうか。
- 【社長】
- 風通しのよい組織風土の改革に従来から取り組んできて、なかなか不祥事が収まらないのではないかというのはご指摘のとおりだと思います。これは、この項目とこの項目が終わったら終わりということにはならず、やはり継続的にいろいろ取り組みをしていかなければいけないと思っています。これがどのくらい終わったか、何%終わったかということは、なかなか言いがたい部分もありますが、例えば日本郵便では、ユニバーサルサービスを含めて事業を行っている私どもの役割は何なのかということも含めて、全員が参加するスモールミーティングを繰り返し行い、一人一人まで浸透させていく、そういったことに取り組んでいるところです。それから、グループとしても考えたいのは、今、調整をしているところですが、管理者についても、当然発言なり何なりというのが、部下社員に対して相当の影響が出てきますので、管理者になるときに、ちゃんとした意識づけだとか、あるいは業務の知識、今回の点呼の問題などもそうですけれども、しっかりと教える必要があると思います。
その点を振り返ってみますと、各支社任せになっていたりする部分もあるので、新任の管理者に対してカリキュラムを統一してやっていかなければいけないといったことは来年度に向けて、今、郵便とも相談を進めているところです。今申し上げたところは一例ですけれども、私どもに不十分なところが多々あるということを常に念頭に置きながら、少しでも改善できることを一つ一つ積み上げていきたいというのが今の状況です。
- 【記者】
- ずっと前なのですけど、郵便物が配達されてなくて、自分のロッカーに荷物が入っていて、いや、これは何だって話になったときに、その人は、業務があまりに多すぎて、もうこれ以上配達は無理だというようなことがあったのだと思うのですよ。そういう話だったのですけれども、結局、それを上の人に言うことができなかったから、そういうロッカーに入っちゃったり家に持って帰ったりとかになっちゃうのだと思うのです。そういったことを、スモールミーティングというところでどのくらい言えるかということなのだと思うのですけど、そういう風土づくりというのを、これからミーティングという形式的な、日本郵便、ミーティングが大好きで、それにうんと時間使っているにもかかわらず全然効果がなかったりするのですけれども、そういう、何というか、根本的なところから変えるにはどうしたらいいと思いますか。
- 【社長】
- まさに、これだけやればいいということはありません。今のお話ですと、そうしたミーティングはミーティングでもちろんやる必要はあると思いますけれども、どうしても、直属の上司には、言いにくいということもあるのかもしれません。これは、既に取り組んでいると思いますけれども、例えば新しく入ってきた、特に仕事に慣れていない社員に対しては、直属の上司以外の人が巡回する中で、業務の負担の状況をフォローしたり、直属の上司だとなかなか言いづらい話を聞いたりする必要などがあると思います。今申し上げたような、効果がありそうなものをいろいろ組み合わせながら積み重ねていくしかないと思っています。
いずれにしましてもそれを一つ行ったからといって、それで終わり、全部完成ということはありません。ミーティングの中身も、単に上司が何か一方的にしゃべるだけのミーティングでは、全くコミュニケーションは改善しませんので、今想定しているのは、どちらかというと、相互に意見を言っていただくような場をつくりたいということですけれども、これもどういうミーティングの仕方をするのかという、やり方を周知、浸透させていかなければいけないと思いますので、そういった試行錯誤を繰り返しながら、やるしかないというのが状況です。特効薬があれば、ぜひ教えていただきたいと思います。
- 【記者】
- 私、25年前にNTTを担当していたのですけれども、これと同じ風通しのよい組織改革というのが、そこの経営の課題になっていて、でも、NTTさんって、いろいろな事業も、いろんな形でやっていて、いろいろなことを、下から上がってくることをやってきているみたいなのですけれども、そのころからもちゃんと上がってやってきていたのですけども、組織風土の改革と言っていたのですけど、うまく今やっているのじゃないかと私は、最近詳しくわかりませんけれども、ちょっと一度、NTTさんに聞いてみたいなと思ったりもしていたのですけれども、できたら取材してきます。
- 【社長】
- ありがとうございます。いずれにしましても、私どもにはまだまだ課題が多いので、そうしたアイデアだとかご意見を頂戴しながら、さまざまな取り組みを進めていきたいと思いますので、ぜひいろいろとご教示いただければと思います。
- 【記者】
- よろしくお願いします。2点お願いしたいのですけど、1点目が、先ほどのロジスティードさんのお話で、株式の保有比率について、まず、きちんと成果を出して、何年かたった上で考えることとおっしゃっていたと思うのですけど、何年かというのは、結構長いスパンでお考えになっているのか、それとも、最低1年ぐらいの、そういう、何年かといっても、やっぱり1年ぐらいでちょっとやっぱりある程度成果を出さないとみたいな、そういう感じでお考えになっているのか、その辺りの、何というか、時間軸というか、その辺はどういうふうにお考えになっていますでしょうか。
- 【社長】
- 株式の取得については、相手がある話なので、何年かということはありませんが、成果について申し上げますと、こういうことを言いますと担当は大変だと思うかもしれませんが、やはり出資をした以上、1年程度の中で、こういった成果があったということを、当社として日本郵便をモニタリングするときには、確認をしていきたいと思っております。「3年も4年もかけて成果があがるので、1年目は何も成果がなくてこれからです」というのでは、ちょっとスピード感としてはどうかと思っています。ただ、出資の議論を確認する限り、これまでもロジスティード様といろいろなやりとりをしていて、相当蓋然性が高いということであり、投資を決定していますので、今まで、ゼロで全く何もないところから、これからシナジー考えますということではありません。したがって、そういう意味では、先ほど申し上げましたように、それほど遠からずシナジーが出てくるものだと期待をしているところです。
- 【記者】
- あと、すいません、もう1点、日本郵便さんが酒気帯びの確認といいますか、全国の支社でチェックされていて、結構、いまだに業務開始前のチェックで酒気帯びを確認されるケースっていうのが、まだゼロになってないっていうのは、それに対していろいろな評価はあると思うのですけれども、こういう状況になっている中で、いまだゼロになってないっていうことに関しては、率直にどういうふうにお考えでしょうか。
- 【社長】
- まだまだ指導を徹底しなければいけないということに尽きると思います。朝の通勤時、要するに乗務する前に確認して分かっているのですが、いずれにしろ、お客さまに対して、郵便や荷物をお届けする事業者として、当然二輪なり車を運転しますので、その自覚を促していくこと、これは大前提です。そういった点で、これも先ほどと同様ですけど、繰り返しやっていくことしかないと思います。最後の一人までということは、時間がかかりますが、絶えず啓発して指導していきたいと考えているところです。
- 【記者】
- すいません。やっぱり不祥事が山積しているという残念な状況であるのですけども、これが、決して全てに、影響だとかそういう気は全くありませんけども、でも、やっぱり大きく影響しているのではないかという感じがいたします。例えばですね、やっぱりどうしても利益をなかなか出しづらい、郵便事業なんかもそうですし、郵便局窓口事業なんかもなかなか利益出しにくい中で、利益を出さなくてはいけないというプレッシャーがかなり大きかったとかですね、いろいろなことがあったと思うのですね。根岸社長は、プロパーという立場でいた中で、やっぱりこのどうしても、組織風土の変化とか、そういったものがあったというふうなことは感じますでしょうか。
- 【社長】
- 利益を出すか出さないかというのと、しっかりとやらなくてはいけないことは別問題なので、例えばかんぽ生命の問題が典型だったのかもしれませんけれども、やはり数字を上げるためには何でもやっていいという風潮、一部そういう受け止め方をできるような指導になってしまっていたという点については、それは反省すべきだと思うのですが、これはただ、民営化したこと自体問題かというよりは、どちらかというと、マネジメントの仕方としての問題だったと思っております。
それと、組織風土の、コミュニケーションがとりにくいところは、これは民営化以降そうなったのかというと、従来の組織の中でも多かれ少なかれそういった面はあったのではないかと思います。世の中もそこはもっと風通しよくしようだとか、それからハラスメントについても、従来だと恐らく許容されたような言い方も、今だとそれはもう絶対駄目ですということになっている部分が、多々あろうと思います。ある意味その環境変化に十分対応できてなかったところが、当グループは大きいのではないかと思っております。やはり私どもは社員数も多く組織も大きいので、どうしても自分たちの中での論理でやってきたルールに引きずられた部分があって、その辺りが改革できなかったところですので、今回の一連の不祥事についても、根本的に直そうと思えば、そういったところを世の中の常識に照らして、説明責任を果たせるような行動なのかどうか考える必要があります。それは、個々でこれをやってはいけないというのはもちろんありますけれども、それ以前に、こういうことを全体としてやったら説明責任を果たせないのではないかという共有が一定程度できないと、新しいものに対応できませんので、そうしたところも含めて、組織改革、風土改革するという考え方に一緒に変えていく必要があるのではないかと改めて思っております。
- 【記者】
- よろしくお願いいたします。点呼の関係でまずお伺いしたいのですけども、根岸社長は、前歴で東海支社長も務められていました。日本郵便が4月に公表した全国調査の結果の中でも、東海支社管内でもですね、不適切点呼の数が非常に多くて、地域別に見ても割合はかなり上位に入るというか、高いほうだと思います。こちらを、結果として監督がしっかりできていなかった部分もあるのかなと思うのですけれども、その部分に関する責任といいますか、どう考えていらっしゃるのかっていう部分をお願いいたします。
- 【社長】
- それはご指摘のとおり、東海支社長を2年間務めておりましたので、最終的な責任は支社長にありますので、責任は十分あると思っていす。事実、そういった意味では、支社長としての処分としては、日本郵便の前社長の千田がご報告したときに処分の対象にも入っておりました。
そうした経験の中で、どこまでが自分として把握できなかったのか、その点をよく反省し顧みて、日本郵便の現社長の小池とも、それを踏まえて、どのようにしたらそれを再演しなくて済むのだろうかということを議論しているところです。
- 【記者】
- ありがとうございます。それと、不配の関係でも1個お伺いしたいのですけども、これまで、非公表にする、あるいは公表するっていう判断ですね、この部分は、例えば東海支社長でいらっしゃったときもそうですけども、こういった判断っていうのは、経営陣としては、何かこの判断にかかっていた部分はあったのかどうか、その辺教えてください。
- 【社長】
- 非公表の部分については、これはどちらかというと、本社で定義していまして、東海支社長時代は、それに当てはめて、単純に対応してきたということです。
ただ、それ以前で言いますと、日本郵便の本社におりましたので、従来、やはり私どもいろんなところがどうしても、犯罪認定するものであるかどうかといったところに議論が引きずられたきらいがあったと思います。先ほどのご質問にありましたように、民営化して変わったところとか変わってないところの議論の中では、ここは従来の考え方に引きずられた部分があったのは否めないと思います。
したがって、犯罪認定したものだけを公表すればよいといったような、やや視野が狭い近視眼的な対応をとっていた部分についての責任は、従来からそうしてきた部分がありますけれども、やはり本社にいた者として、そういった解釈を変え得なかったところについては、相応に責任を負っているものと思っています。
- 【記者】
- ありがとうございます。それと、今後、非公表事案、公表されるってことだったのですけども、具体的に、これ、いつ頃の、2カ月も3カ月もかからないとおっしゃっていましたけども、今月中なのかあるいは11月中なのか、この辺のスケジュール感をお願いします。
- 【社長】
- そういう意味では、11月いっぱいまでを見越していると2カ月になってしまいますので、11月末まではかからないという意味で、2カ月もかからないと申し上げました。ただ、そこが10月中にできるか、ちょっと11月の頭になるかというところは作業にもよりますので、そこについてはまだ確定したことは申し上げられない状況です。いずれにしましても、今申し上げた程度のスパンの中では対応できそうだということで聞いておりますので、しっかり対応していきたいと思っております。
- 【記者】
- 非公表事案について追加でお伺いしたいのですけれども、先ほどもおっしゃっていたように、過去さかのぼって公表する対象として、2021年から24年で30件くらいということでおっしゃっていたと思うのですけれども、これは、おっしゃった中では、犯罪には該当しないと判断された、適切に届かなかった事案ということだと思うのですが、もう少し具体的にその30件の事案というのは、定義というかですね、どのように位置付けられていた事案ということでしょうか。
- 【社長】
- 不取り扱いで、要は、故意、あるいは事故で誰がやったのかわからないけれども、長期間配られなかった、そういった事案が中心だと聞いていますが、そのほか具体的なものについては、担当からお答えさせていただきます。
- 【事務方】
- 対象となった事案については、例えば職場の中で、郵便物が発見された事案であったりとか、それから、空き家の中から出てきた事案など、行為者が不明だったりした事案など、そういったものもあったりしたかと思います。いずれにしても大半は、遅れた場合は、お客さまにご説明してお返しするというような対応を行っておりますが、そこも含めて、本件は精査をしておりますので、公表のときに、ちゃんとご説明できるようにしたいと考えております。
- 【記者】
- ありがとうございます。今回の適切に届けられなかった事案の中で、当然それ自体利用者には不利益が及ぶということだと思いますけれども、さらに非公表にしていたことによって、適切に届かなかったことを差出人が気づけないおそれもあるということがこの非公表にしたことによって、こうむってしまう不利益だと思います。そういうおそれがある事案を非公表にするという判断によってつくってしまっていたことについて、どのような責任があるというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
- 【社長】
- 非公表としてもお客さま、差出人が分かっていれば、個別に対応したものもあったのだと思いますけれども、ただ、例えばDMなど、お客さまは届くか届かないかわからなかったけれども、本来届くものであったとしたら、対応が変わったかもしれないというようなもの、あるいは、もしかしたら自分のところに届かなかったかもしれないと、何かお感じになった可能性とかを含めますと、やはりそこについては、個々にどれと明確に言えませんが、やはり何らかの不利益があったのだろうと思います。
そういう意味では、お客さまから郵便なり荷物をお預かりする事業者としては、誠意が足りない行動だったと思っております。反省し、会社として責任を感じているところです。
- 【記者】
- 本当はこれ、今おっしゃった、その先ほどおっしゃった2021年から24年の分というようなのは、これはちょっと確認ではあるのですけれども、総務省の調査を受けて報告した事案のことをおっしゃっているのですね。
- 【社長】
- 30件というのは、もちろん最後は確認しなければいけませんけれども、基本的にはもともと私どもが把握をした事例です。そこにプラスアルファで付け加えるものがあるかどうか、もう少し広く確認する必要はあると思いますけれども、ご指摘のとおりです。
- 【記者】
- それで、その件で言うと昨年の6月にその報告を受けて総務省のほうからですね、その非公表、公表の判断については、改善を促す通知がなされていると思います。で、その通知からですね、今回行政指導を受けてさらに非公表分、過去分もさかのぼって公表するというふうな判断に至るまでに、この通知後どのような社内で議論がされてきて、なぜ今回こういう判断をするに至ったのか、可能な範囲でお伺いできますでしょうか。
- 【社長】
- お客さまにご迷惑をかけている事案であり、潜在的なご利用者の方もいらっしゃいますので、広くお知らせすることが適切だと直近に判断しました。そういう議論は日本郵便の中でも行われ、私もそうだと思っております。昨年来で言いますと、犯罪としなかった事案であっても必要があれば公表しようということで、行っていたようなのですけれども、その必要があればというのをかなり小さくとって、要するに原則として公表すべきという判断ではなくて、犯罪ではなくても公表しなければいけない事案について、視野をかなり小さく捉えた部分があったのではないかと思います。視野を小さく捉えていたところはやはり反省すべき点であったと思っております。
それにより、この1年近く、そのまま運用がされていて、実際の運用としては十分な改善が得られないまま、いろいろなご指摘、報道もありましたけれども、そういった中で十分対応できてなかったことを改めて確認いたしました。もう一度整理をして、考え方として襟を正し、正しいあるべきやり方に変えようと、今方針を変えているところです。
- 【記者】
- 通知から、1年3カ月たっておりまして、今おっしゃったように、問題を小さく捉えるようなところがあったということなのですけれども、これは組織、企業の体制であったり、ガバナンス上、どういう問題があったかについてお考えがありますでしょうか。
- 【社長】
- 繰り返しになりますが、いろいろな形で私どものリスク感度が低かったということで反省を申し上げることがこれまでもあったと思います。それらの問題と根っこは同一ではないかと思っております。そういった説明責任を果たすためにはどうするべきかということを考えたときに、その時点で近いような考え方ができたらよかったのだと思いますけれども、そういった議論が不十分だという点については、変えていかなければなりません。変えていかなければいけないけど、変わっていない、というご意見がありますけれども、特に判断をするような役員、部長を含めて、本来あるべきリスク感度を高めるためには、具体的にどういうことをやる必要があるかということを、今回の実例をよく踏まえて改めて認識を新たにしなければいけないと考えています。
- 【記者】
- 今回の過去分も公表するという判断をされたのは、総務省の行政指導が直接の理由なのか。その辺り何かお伺いできますか。
- 【社長】
- ここはいろいろな議論の中での判断であって、100%これですという話ではないかもしれません。総務省の行政指導を受けた後に、総務大臣が会見で、過去分含めて日本郵便に検討させて、という内容のご発言がありました。そこが一つの引き金になったことはあるかと思います。ただ、総務大臣からこうした指摘があったからやるべき話ではなくて、本来そこは自主的に、公表すべき点があればすべきということだと思いますので、そういった点も含めて、まさにリスク感度、やはり説明責任を果たすような取り組みにつなげていきたいと思っています。
- 【記者】
- すいません、最後1点だけ文書の保存期間の関係でもあるとおっしゃっていたそのどこまでさかのぼるのかという問題なのですけど、現状2021年以前のところは文書保存期間の関係から、現状どこまでさかのぼれる、さかのぼろうというふうな今整理をされているか、お伺いできますか。
- 【社長】
- 多分、文書の保存期限は、3年だったり5年だったりとかなり短いので、大きくはさかのぼれないと思うのですが、少なくとも2021年までは、文書そのものがありましたので、そこを中心にと聞いております。それ以前は現実的には大きくはさかのぼれないと思いますが、どこまでできるかは、確認をしておくべきということで、日本郵便で整理をしているところです。
- 【記者】
- すいません、1点だけお伺いさせてください。この部内犯罪認定、非公表にする、しないというのは誰が決めているのかを聞きたいのですけれども。なぜ聞きたいかというと、うちの記事にも出ていたのですが、全く同じ事例なのに、公表だったり非公表だったり、いわゆる宅配ボックスに入れているケースですね。宅配ボックスに入れているのに、意図的じゃないってちょっと考えられないしですね、例えば自家用車に入れているのに、今から配ろうと思ったということはあり得ないし、それは要するに言ったもの勝ちじゃないのかという部分とか、あとは例えばですね、ある郵便局の社員の中には、いわゆる支社が自分たちの評価を気にして、非公表にしているのではないかという疑いも持たれているわけですよ。そうなってくると、誰が判断しているのかって非常に重要になるのかなと思うのですけれども、さっき私が聞き逃したかもしれないですけども、誰が決めているのか教えていただけますか。
- 【社長】
- 日本郵便の経験で申し上げますので、もし何かあれば陪席の者からフォローさせてもらいますけれども、基本的にそういった犯罪の疑いがあるようなものについては、コンプライアンス部署による調査が行われていて、そのコンプライアンス部署による調査で、犯罪に当たるかどうかを判断します。ただ、誰が配達に行ったのか、特定できるかといったこともありますし、郵便物が1日置いてあったときに、それが何かしらの理由で持ち戻りしたけれども、報告はできなかったなど、犯罪とまでは言えないという部分があって、そういった微妙なところについては、弁護士の先生や、場合によっては警察に相談をして決めていると認識をしています。いずれにしても、支社が犯罪としたくないがために、一者だけで決めさせるようなことはなく、いわゆる業務部門とは独立した部門において判断をしています。その判断の是非について、微妙なところありますが、犯罪かどうかについてはどうしても警察との関係もありますので、そのほかの部分を含めてやはり公表するのが適切ではないかと思っております。
- 【記者】
- コンプライアンス部署が判断しているということでよろしいのでしょうか、非公表、公表は。
- 【事務方】
- グループの中で公表、非公表の基準、例えば犯罪事案であるとか不祥事というのは、公表するというものは決めております。犯罪に該当するか、法令違反に該当するかというのは、コンプライアンス部門で調査のうえ、認定し、その後、公表基準に該当するかどうかで判断しています。
- 【社長】
- 要するに、犯罪として認定すれば自動的に公表されますけれども、これまでは犯罪ではなかったと判断したときに、ゼロではないにしても、かなり限定的にしか公表していませんでした。その時点で、非公表のほうによるという形が運用になっていたと思います。
- 【記者】
- 実はわれわれの質問状にもあったのですけども、福岡の事例で、宅配ボックスに、仙台で一応書類送検された同じような事例で、宅配ボックス入れている例があるのですね。個別事案について答えられないということを承知の上でお伝えするのですけれども、人のマンションに入ってですよ、郵便物を入れるという行為がですよ、犯罪じゃありませんというのはどういう認識になっているのかなという理屈も分からないし、犯罪認定は何で日本郵便がするのかなというのも分からなかったという部分もあるので、その部分は付言させていただいて、もし意見があればお伺いしたいなと思っているのですけども。
- 【事務方】
- 当時の判定の、故意性ですとか、そういった犯罪要件に該当するかというものを判断して分かれたのではないかなと思います。公表した事案と公表してない事案のところは内部的な判断をしたところはありますけども、個別事案ですので、詳しいところは今ここでは差し控えさせていただきたいと思います。
- 【記者】
- たびたびすいません、1点だけちょっとお伺いしたいですけど、不適切点呼のところでオペレーションを委託会社とか協力会社とかを使って、もうできているというところだと思うのですけど、それで協力先として、佐川とか西濃とかが上がったと思うのですけど、ヤマトの名前がなかったというところで、今訴訟とかもあっていろいろあると思うのですけど、そういうところがちょっと影響しているのかどうなのかというところと、そのヤマトとの関係性というのが、今そういう協力のところでどうなっているのかというところを教えていただければ幸いです。
- 【社長】
- 特に軽四輪車の場合は佐川様などにお願いをするところがありますけれども、従来から実際に個々人のお客さまに配達するときには、かなり小規模の地元の委託先様を活用させていただいておりますので、まずは地元の配送会社様に多くやっていただけないかと調整しています。それでも足りないところは佐川様や西濃様などにお願いすることになります。
前回のトラックの部分についても、ヤマト様にもいろいろとご相談差し上げたと聞いておりますけれども、結果として、いろいろなニーズに佐川様、西濃様のほうがより多く対応可能ということであって、いろいろと訴訟の問題を抱えておりますけれども、この問題については別問題で、結果としてうまくお互いの需要と供給が合致しなかったと私は理解しています。
- 【記者】
- すいません、先ほどのロジスティードさんのところで、根岸社長は物流分野、事業の強化についてはM&Aを含めてさらに考えていきたいと、こういうふうにおっしゃったのですけども、これは次期中計に関わることかもしれませんけども、例えば連結子会社化にするのかとか持ち分法適用会社にするのかとか、あと分野については国内コントラクト事業にするのか、倉庫にするのかとか、幹線輸送にするとか、いろいろと選択肢はあると思うのですけども、何か青写真みたいなものをお示しいただければありがたく存じます。よろしくお願いします。
- 【社長】
- まさに次期中計で総合物流企業に向けた取り組みというのは考えていかなければいけない話だと思っています。したがいまして、現時点で今日申し上げた以上のところはなかなかお伝えできるような状況にありませんし、それからロジスティード様に関して申し上げますと、今回、約20%を出資いたしましたけれども、それを連結化するかどうかということについては、現時点で全くの白紙ですので、その約20%の中でどういうシナジーをできるかどうかだと思います。
それから総合物流という意味で申し上げますと、例えばトナミ様ですとか、あるいはJPロジスティクス、もともとトール社の国内部門だったところなど、こういったところの活用もありますので、そういったところを含めて総合物流事業としてどうしていくかを考えていくのだと思っています。
- (※記者会見における発言および質疑応答をとりまとめたものです。その際、一部、正しい表現・情報に改めました。)